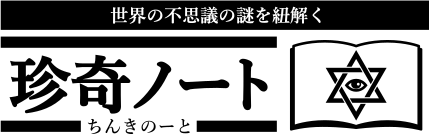『太平記』巻第二十三「大森彦七事」 現代語訳
スポンサーリンク
はじめに(翻訳内容に関する注意点)
以下の文章は、『太平記』巻第二十三「大森彦七事」の原文を読んで、勝手に現代語に「意訳」したものです。なるべく原文に忠実に訳すよう務めましたが、分かりづらいところに関しては多少の省略や加筆修正を行っています。また、専門家ではない素人が訳したものなので、翻訳の誤りや抜け落ち、誤字脱字などがあるかも知れません。そういった点に注意して読んで下さい。なお、サブタイトルは物語を見やすくするために勝手に付けたものです。
大森彦七盛長
暦応5年(1342年)の春頃、伊予国から飛脚が来て不思議な註進があった。その詳細を述べると、伊予国の住人に大森彦七盛長(大森盛長)という者がおり、その心はあくまで不敵で、力は世の常人よりも勝れていた。まことに血気盛んな勇者であると言える。
去る建武3年(1336年)5月に将軍(足利尊氏)が九州より攻め上った時、新田義貞は兵庫の湊川で支えて合戦をしたが、この大森の一族は細川卿律師定禅(細川定禅)に従って手痛く戦って、楠木正成に切腹させた者である。そのため、その勲功は他と異なり、数箇所の恩賞を賜った。これを悦び誇って、一族ともどもに様々な遊宴を尽くして豊かな暮らしをしていたが、猿楽は齢を延ばすということで、御堂の庭に桟敷を打って舞台を造り、種々の風流を尽くそうとした。これを聞いた近隣の者は、貴賤を問わず群れ集まった。
道端の怪異
彦七(大森盛長)も その猿楽の衆であったので、様々な装束を下人に持たせて楽屋に向かったが、山際の細道を通った時に18歳ばかりに見える女房が赤い袴に柳裏の5つ衣を着て、鬢(びん)を深く削いで、差し出た山端の月を眺めながら独りで佇んでいた。そこで彦七は女を見て、こんな田舎にこのような女房がいるとは、一体どこから来たのだろうか、またどこの桟敷に行こうとしているのか、と目を離さずにいた。すると、女房は彦七に向かって「路芝の露を払う人もおらず、道に迷って困っています」と言ったが、その様子は悲しげで いかなる荒夷(勇猛な蛮族)であっても同情しないような者は居ないように思えた。
彦七は怪しんで、どこ宿の妻であるかも分からず、善悪も知らずに関わるのはどうかと思いながらも、すっかり気力を無くした姿を放っておけずに「道はこちらです。桟敷の宛てが無いのでしたら、たまたま用意した桟敷がありますので、そこにお入りください」と言うと、女は微笑みながら「嬉しいです。ならば桟敷に参りましょう」と言って、彦七の跡を付いて歩き出した。
羅綺(らき)にも劣ったその姿は本当に辛そうであった。未だに一歩も土を踏んだことの無いように思え、歩くのに難儀している有様を見て、彦七は黙っていられずに「あまりに霞が深いので、向こうまで背負って差し上げましょう」と言って前に出て跪いたが、女房は少しも遠慮せずに「恐れ入ります」と言いながら、やがて後ろに寄りかかってきた。白玉か何かと問うた古にも このようだった思いだったのかと感じながら、嵐によって散る花が袖に掛かるよりも軽やかに、梅花の匂いも懐かしく、踏む足もたどたどしく、心も空に浮かれつつ、半町ばかり進んでいった。
それから山陰に月が少しかかって暗くなったところで、美麗であった女房が俄に身の丈8尺(約2.4m)の鬼となった。その眼は朱を溶いて鏡の面に注いだようであり、上下の歯は食い違っていて耳の根まで広く裂け、眉は漆を百回塗ったように額を隠しており、振り分けた髪の中から5寸(約15cm)ばかりの牛の角が鱗に覆われて生え出ていた。その重さは大盤石を推しているように重く、彦七の背から髪を掴んで虚空に昇ろうとした。
彦七は元来強かな者だったので、鬼を引っ掴んで深田の中に転び落ちて「この盛長が化物を取り押さえたぞ、者どもよ此処に寄れ」と呼びつけたので、これを聞いた者どもは太刀や長刀の鞘を外して駆け寄ってきたが、その時に鬼はかき消すように失せてしまった。そこで彦七は若党・中間らを引き集めたものの、呆然として人心地を失っていたので、これは只事ではないとして、その夜の猿楽は中止にすることにした。
楠木正成の亡霊
しかし、これまで身につけた猿楽を披露せずに終えるわけにはいかないと、また吉日を定めて、堂の前に舞台を敷き、桟敷を打ち並べると、見物の人々も集まったので、猿楽が再開された。そこで猿楽が始められて その半ばに差し掛かった時に、遥か遠くの海上に唐笠ほどの大きさの光る物が2,300ほど現れた。これは漁師の焚いた漁火か、鵜舟に燈された篝火かと思われたが、そうではなく、一叢に立った黒雲の中に玉の輿が担ぎ連ねてあり、恐ろしい鬼のような姿の者が その前後左右に連なっていた。また、その一行の後ろには様々な鎧を着た兵が100騎ばかり細馬に轡を噛ませて供奉していた。それが段々と近づいて来たが、その容貌を確かめることはできず、黒雲の中に時々稲光が輝いて、それは猿楽の舞台の上を覆って森の梢に留まった。
見物人は皆 肝を冷やして見上げていたが、その時に雲の中から高い声で「大森七彦殿に申すことがあり、楠木正成が参った次第である」と呼びかけた。彦七はこのようなことを恐れぬ者だったので、少しも臆せずに「人が死んで再び帰ることなどない。きっと、その魂魄が霊鬼と成って現れたのだろう。それは良いとして、楠木殿は何事の用事で現れて、この盛長を呼び出したのだ?」と問うた。
すると、楠木は「この正成が存命の間、様々な謀を廻らせて相模入道の一家を傾けて、先帝の宸襟を休め参らせて、天下統一に帰して聖主の万歳を仰ごうとしたところ、尊氏卿や直義朝臣が忽ち虎狼の心を挿し挟み、遂に我が君(後醍醐天皇)を傾けた。これによって忠臣・義士の屍は戦場に曝し、それは悉く修羅の眷属になって瞋恚を含む心は止むことはない。正成はこれらの者と共に天下を覆そうと謀っているが、貪・瞋・痴の三毒を表す故に必ず3つの剣が必要になる。我ら大勢は、憤怒の悪眼を開いて刹那に大千界を見るに、願うところの剣は我が朝の内に3つ揃っている。その一つは日吉大宮にあって法味に替えて申し賜った。もう一つは尊氏のもとにあるが、寵愛する童と入れ代わって乞い取った。もう一つは御辺(大森盛長)が今腰に挿している刀である。知らないと思うが、その刀は元暦の古に平家が壇ノ浦で滅びた時、悪七兵衛景清(藤原景清)が海に落としたものを江豚(イルカ)という魚が呑んで、讃岐の宇多津の澳にて死んだ。それが海底に沈んで100年あまりを経た後、漁夫の網にかかって御辺のもとに伝わった刀である。もし この刀を我らの者が持つならば、尊氏の代を奪うことなど容易いだろう。そこで急いで参らせよとの先帝の勅定を正成が被って此処に来たのである。早く渡すべし」と言ったが、それを言い終えるまでに東西には雷が鳴り渡っており、今にも落ちてこようとしているように聞こえていた。
盛長はこれにも臆さずに、刀の柄が砕けるほどに握って「さては、先日 美女に化けて私を誑かそうとしたのも、御辺(楠木正成)たちの所業でなのだな。御辺が存命の時から常に申してきたことだが、どんなに重宝であっても御用とあれば惜しまずに渡しただろう。ただし、この刀を以って将軍の世を滅ぼそうとするならば、渡すわけにはいかない。この盛長は不肖の身であるが、将軍方に参じて無二の者と知られるようになり、その厚い恩賞を被って一家を豊かにして過ごしてきた。そこで、この猿楽をして遊ぶことも、ひとえに武恩のよろこびである。およそ勇士の本意を述べれば、ただ心の不変を以って義をなすことであろう。そのため、たとえ身をずたずたに裂かれ、骨をいちいち砕かれようとも、この刀を渡すことはないだろう。よって、早々にお帰りになられるが良い」と言って、虚空を睨んで立っていると、正成はとても憤慨して「なんとでも言うが良い、最後には取ってやるぞ」と罵って、元のように光を放ち、海上の遥か遠くに飛び去っていった。これを見た見物人は貴賤を問わず、今にも天に引き上げられるかと思って、肝魂も身に添わぬほどの恐れをなし、子は親を呼び、親は子の手を引いて、四方八方へ逃げ去っていったので、今夜の猿楽も2,3番を終えたとことで中止になった。
楠木正成の再来
その後、4,5日を経ると、激しい雨に風も凄まじく吹き騒ぎ、時々雷光を放つようになったので、盛長は「今夜、以前の化物が来ると思うので、防戦を備えをして待ち構えよ」と言って、中門に敷皮を敷いて、鎧で身を固め、二所藤の大弓に数多の征矢を抜き散らし、鼻膏を引いて、化物がやって来るのを待っていた。
それから夜中を過ぎた頃、曇り無き月夜の空が俄にかき曇って、黒雲が一叢に立ち昇って周囲を覆い始めた。そして、雲の中から「大森殿は此処におられるか、先度 仰せのあった剣を急ぎ参らせよとの綸旨を被って、その勅使として正成が再び参った」という声がしたので、彦七も庭に出て「今夜に必ず来ると思って宵から待っていたぞ、はじめは天狗や化物が化けているのだろうと思って細かい問答に及ばなかったが、今確かに綸旨を携えていると聞いて、間違いなく楠木殿であると確信した。不審と思われるかも知れないが敢えて聞きたい。まず数多の御伴を連れているように見えるが、それは何者なのだ。御辺(楠木殿)は六道四生の間のどこで生まれたのだ?」と尋ねた。
そこで、正成は庭前の柳の梢に降りて「正成と相い伴う人々は、まずは 後醍醐天皇・兵部卿親王(護良親王)・新田左中将義貞(新田義貞)・平馬助忠政(平忠政)・九郎大夫半官義経(源義経)・能登守教経(平教経) の7人である。その外の輩は申すに及ばす、数えるに暇なし」と答えた。そこで盛長は「そもそも先帝(後醍醐天皇)はどこにおられるのか?また、相い従う人々はどんな姿をしておられるのだ?」と問うと、正成は「先朝(後醍醐天皇)は元は摩醯首羅王の所変であり、今は帰って欲界の六天におられる。従う人々は悉く修羅の眷属となって、ある時は天帝と戦い、ある時は人の世に降って、瞋恚強盛の人の心に入れ替わることもある」と答えた。
次に盛長が「では、御辺(正成)はいかなる姿であられるのだ?」と問うと、正成は「それがしは最期の悪念に引かれて罪障が深かったので、今は千頭王鬼となって七頭の牛に乗っている。疑っているのならば、その姿を見せよう」と答えて、松明を14,5本同時に振り上げたので、盛長が虚空を遥かに見上げると、雲の中に12人の鬼どもが玉の神輿を担ぎ上げていた。次に兵部卿親王が八竜に車をつなげて従っており、新田義貞は3000騎あまりを率いて前陣に進み、源義経は鎧兜で武装した数百騎を率いて後陣を支えていた。その後ろに平教経が300艘ばかりの軍船を波に浮かべており、平忠政は赤旗を一流に差し上げて、これも後陣に控えていた。
また、虚空が遥かに引き下がり、楠木正成の姿が顕になったが、湊川の合戦で見た時と少しも違わず、紺地錦の鎧直垂に黒糸の鎧を着て、頭が7つある牛に乗っていた。この他にも保元・平治の乱で討たれた者どもや、治承・寿永の乱で滅んだ源平両家の輩、この頃の元弘・建武の乱で滅んだ兵どもがおり、人に名を知られるほどの者は皆 甲冑を帯びて弓矢を携え、虚空の十里ばかりの間に隙間なく見えていた。この有様は、ただ盛長のみに見えていて、他人の目には見えていなかった。
そこで盛長は左右に「あれが見えぬか」と言おうとすると、正成の一行は風に吹かれる雲のように忽然と消え失せてしまい、ただ正成の声ばかりが残っていた。盛長はこれ程の不思議を見ても心は不動で「『一翳眼にあれば空華乱墜す』と言うように、千変百怪など驚くに足らない。たとえいかなる第六天魔王どもが来ようとも、この刀を渡すわけにはいかない。よって、例の手の裏を返すような綸旨を賜ったと言えど無益である。各々は早々に帰り給え。この刀は将軍(尊氏)に参られるものだ」と言い捨てて、盛長は屋内に入っていった。これに正成は大いに嘲笑って「この国がたとえ大陸と繋がったとしても道を容易く通すことはない。ましてや海上を通ことなど決して無いだろう」と声を合わせて一斉に笑うと、西を指して飛び去っていった。
その後、盛長は正気を失って、休むこと無く山を走り回ったり水に潜ったりした。この状態では太刀を抜いたり矢を放ったりできないので、一族どもは集まり、盛長を一間ほどの場所に押し込めて弓矢や兵杖を帯びて警固した。
牛の怪異
ある夜、また雨風や稲妻が起こったので、楠木正成が来たかと怪しんでいると、案の定 盛長が寝ている枕元の障子を踏み破って、数十人が入ってくる音がした。これに警固の者どもも起きて すぐに太刀や長刀の鞘を外し、夜襲だと思って敵の姿を捜したが、その姿は無かった。これはどうしたことかと思っていると、天から熊のような毛に覆われた長い手が下りてきて、盛長の髻を取って宙に引き上げて破風の口から出ようとした。そこで盛長は引き上げられながらも件の刀を抜いて、化物の中心に刀を3分ほど刺し入れると、化物は弱ったように破風から広庇の軒の上に転び落ちたので、盛長は化物を押し付けて7分まで刺し通した。すると、化物の急所に刺さったのか、脇の下から鞠のようなものを吐き出すと、虚空を目指して上がっていった。
また、警固の者どもが梯子を掛けて軒の上に登ってみると、そこに一つの牛の頭があった。「これはきっと楠木正成の乗っていた牛か、そうでなければその魂魄が宿ったものだろう」として、この牛の頭を中門の柱に結びつけて置いたが、夜通しずっと泣き喚いて動き続けるので、打ち砕いて水底に沈めた。
蜘蛛の怪異
それから、次の夜も月が曇って風が吹き荒れるといった怪しい雰囲気だったので、警固の者どもは大勢で遠侍に詰めて、夜通し碁や双六などを打って眠らないように警固に勤めた。夜半を過ぎると上下100人あまり居た警固の者どもは同時に「あっ」と言ったかと思えば、皆 酒に酔った者のようになって、頭を垂れて眠ってしまった。
その座の中に居た禅僧一人だけは眠らなかったが、灯火の影を見ると、大きな寺蜘蛛(やまぐも)が一匹 天井から下がってきて、寝入った者の上を這ってまた天井に上がって行った。その後、盛長が来てみると、蜘蛛は人と組んでいるように見え、その上下にうごめいていた。これは敵わぬと思って「寄れや者ども」と呼びかけたが、傍に伏せている者どもが起き上がろうとしても、柱に髻を結び付けられたり、自分の手足を他人の手足に結び付けられたりしていて、まるで網に掛かった魚のように動けなくなっていた。
この禅僧はあまりの不思議さに走りたって見に行くと、剛力の者どもが僅かな蜘蛛の網に手足を繋がれて、まったく身動きが取れない有様だった。しかし、盛長が「化物を取り押さえたぞ、火を持って参れ」と申し付けたので、動ける警固の者どもがようやく起き上がり、蝋燭を灯して駆けつけると、そこには盛長が押さえつける膝を持ち上げようと、蜘蛛がもぞもぞと動いていた。そこで諸人が手に手を重ねて、逃すまいと押さえつけると、大きな土器が壊れる音がして、微塵に砕けてしまった。
その後手を退けて見ると、曝された死人の首が眉間の中間から砕けて残っていた。これに盛長は大きく息を吐いて、しばし心を鎮めて自らの腰を探ってみると、この蜘蛛の化物に刀を取られて鞘ばかりが残っている。これを見た盛長は「私は既に疫鬼に魂を奪われてしまった。今はいかに猛く思っても敵うまい。我が命の事はどうでもよいが、将軍(尊氏)の御運はどうなることか」と歎いて、顔色を変えて涙を流し、わなわなと震えたので、この様子を見ていた者は悉く身の毛のよだつ思いに苛まれた。
こうして夜が少し更けて有明の月が中門に差し入った頃、盛長が簾を高く巻き上げて庭の様子を眺めていると、空から毬のような物が光って草叢の中に落ちてきたので、一体何だと駆けつけてみると、そこには先程 盛長に押しつぶされた首の半分を件の刀が柄口まで貫いたものが落ちてきた。不思議なことだといえど、疎かにはできないので、やがて刀に刺さった頭を取って火に投げ入れ、そこから踊り出たものを金鋏で焼き砕いて捨ててしまった。
女の首の怪異
事が静まった後、盛長は「今はもう化物も来ないだろう。その故は楠木と相伴う者が来ること既に7度である。これから来れる者もおるまい」と言うと、諸人も「確かに」と納得した。しかし、その時に虚空からしゃがれ声にて「7人には限るまいぞ」と嘲笑う声がしたので、これはどうしたことかと驚いて諸人も空を見上げると、庭の鞠の懸かりに、眉太に作り、お歯黒をした女の首が現れた。その面は4,5尺(約1.2~1.5m)もあるように見えたが、乱れ髪を振り上げて目も美しく笑うと「恥ずかしや」と言って後ろを向いた。これを見た者は怯えて、同時に皆 倒れ伏した。
大般若経
このような化物は蟇目(鏑矢)の音を恐れるものであるとして、毎夜 番衆を置いて宿直をさせ、蟇目を射させることにすると、虚空にどっと笑う声が その度に天に響き渡った。そこで陰陽師に門を封じさせようとして、符を書かせて各門に貼り付けたが、目に見えぬ者がやって来て符を取って捨てたので、さてどうしたものかと思い悩んでいると、彦七(盛長)の縁者の禅僧が言うには「そもそも今現れている悪霊どもは、皆 修羅の眷属であるので、これを鎮める謀を案ずれば、大般若経を読むのが不可欠である。その理由は、帝釈天と修羅が須弥山で合戦した時に、帝釈天の軍勢が勝った時は修羅は小身になって藕絲の孔の中に隠れ、修羅が勝った時は須弥山の頂上に座って手に日月を握って足で大海を踏んだ。こればかりでなく、三十三天の上に攻め上って帝釈天の居所を追い落とし、欲界の衆生を悉く我が物としようとしたので、諸天の善神が善法堂に集まって般若を講じたのである。この時、虚空より輪宝を下して剣戟を雨のように降らせ、修羅の輩をずたずたに裂き切ったという。よって、須弥の三十三天を領した帝釈天であっても、我が敵わぬところには法威を以って魔王を降伏したのである。言うまでもなく、薄智の凡夫であっても、法力を借りずに退治することはできまい」ということなので、これに納得して すぐに僧衆を呼び出して真読の大般若を日夜六部まで読ませた。
すると、まことに般若購読の法力によって修羅は威を失ったのか、5月3日の暮れ頃に導師が高座の上から啓白の鐘を打ち鳴らすと、俄に天がかき曇り、雲の上に車を轟かせて、馬が馳せ違う音が絶え間なく聞こえてきた。矢先が甲冑を射通す音は雨が降るよりも茂く、剣戟を交える光は輝く星に違いは無かった。そのため、見聞きする者は推し並べて肝を冷やして恐れ合った。この戦いの声が止んで天が晴れると、盛長の狂乱は全快して、正成の魂魄は夢にも全く出なくなった。それにしても大般若経の真読の功力によって、敵軍に威を添えようとした楠木正成の亡霊は静まったので、脇屋刑部卿義助(脇屋義助)・大館佐馬助(大館氏明)をはじめとして、土居(土居道増)・得能(得能通綱)に至るまで、あるいは誅され、あるいは切腹して、失せてしまった。
伝え聞くところによれば、天竺の班足王は仁王経の功徳によって千王を害することを止めたという。また、我が朝の楠木正成は大般若の購読によって三毒を免れることができた。まことに鎮護国家の経王は人民の利益のための要法であった。
その後、この刀は天下の霊剣として、委細の註進を副えて上覧に備えると、左兵衛督直義朝臣(足利直義)はこれを見て「事実ならば、末世の奇特はこれに勝るものなし」と言って、上を作り直して、小竹作りと同じように賞翫(珍重)したという。砂子に埋もれて年久しく断剣のようだと言える この刀は盛長の註進によって凌天の光の如く輝いた。不思議なことである。
スポンサーリンク
|
|