アルゲンタビス・マグニフィセンス ― かつて実在した南米の巨大鳥 ―

アルゲンタビスとは、中新世に南米に棲息していた大型の古代鳥のこと。
翼長7メートルを超える巨大な翼を持ち、コンドルのように空を飛んでいたと考えられている。
なお、化石はアルゼンチンで発見され、この名は「壮大なアルゼンチンの鳥」を意味しているという。
基本情報
概要
|
|
アルゲンタビスは、800万~600万年前に南米に棲息していた大型の猛禽類であり、その化石から推定されるサイズは 体長1.5メートル、翼長7メートル、体重80キロ ほどもあるといわれている。また、巨大なクチバシは幅広で細長く、先端がワシのように曲がっており、頑丈で大きな足を使って容易に歩くことができたと考えられている。
なお、アルゲンタビスの翼長は、現存する最大級の鳥類であるワタリアホウドリ(3.6メートル)やアンデスコンドル(3.2メートル)の約2倍であり、2014年にペラゴルニス・サンデルシ(北米で化石が発掘された絶滅種の鳥)が新種と認められるまで、飛行可能な鳥類としては史上最大であった。
冒頭の画像は復元された模型だが、一緒に写っている人と比べてみても非常に大きいことが分かる。ちなみに、この模型の写真は、UMAとして知られるビッグバード(サンダーバード)の写真として紹介されていることも多い。
・翼長は5~7.5メートル
・体長は1.3~1.5メートル
・体高は1.5~2メートル
・体重は70~80キロ
・幅広で細長いワシのようなクチバシを持つ
・歩行できる巨大で頑丈な足を持つ
・化石はアルゼンチンの中部と北西部の中新世の地層から発見された(サンプルは少ないとも)
アルゲンタビスの生態
アルゲンタビスの生態は、現存する鳥類の生態と比較して、2年ごとに1キロ程度ある卵を1~2個産み、その卵は冬の間に孵化して16ヶ月後に独立するようになり、約12年かけて完全に成熟すると考えられている。
また、捕食されることはほとんどなく、主な死亡原因は 老死、事故死、病死など と推定されているようだ。
アルゲンタビスの飛行方法
アルゲンタビスの飛行方法は、体重や翼の構造から、山の斜面や逆風を利用して離陸するという上昇気流に任せた飛行方法を取っており、羽ばたきながら飛行したのは短時間であったと考えられている。
なお、この方法は現存するアンデスコンドルの飛行方法と同じものであり、熱上昇気流が発生しやすい現地の気候からも この方法で飛行可能であるといわれている。
アルゲンタビスの給餌方法
アルゲンタビスは現存するコンドルやハゲタカのように、上空から餌となる動物の死骸を見つけて その腐肉を食べていたと考えられている。その理由として、アルゲンタビスは一度着陸すると すぐさま飛び立つことができないため、地上にいる間はティラコスミルスなどの肉食動物に襲われる危険性が高いためだといわれている。
その一方、クチバシの形状から、テラトルニスコンドル(コンドルのような古生物)のように積極的に狩りをしたという意見もあり、もし そうしたならば、着陸せずに獲物を捕らえて、そのまま丸呑みにしたと考えられているという。
データ
| 種 別 | 巨大生物、絶滅した生物 |
|---|---|
| 発見地 | アルゼンチン |
| 年 代 | 中新世(800万~600万年前) |
| 体 長 | 1.3~1.5メートル(翼長5~7.5メートル) |
| 備 考 | 史上最大級の鳥類 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
|
|
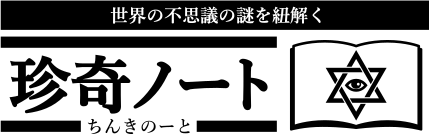


コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿