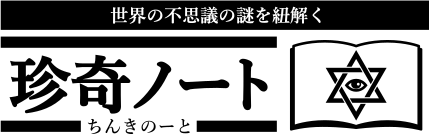白龍の資料

スポンサーリンク
『墨子』貴義(紀元前4世紀〜紀元前3世紀頃)
原文
且帝以甲乙殺青龍於東方、以丙丁殺赤龍於南方、以庚辛殺白龍於西方、以壬癸殺黑龍於北方。
現代語訳
(墨子は言った)「そもそも、天帝は甲・乙の日には東方で青龍を殺し、丙・丁の日には南方で赤龍を殺し、庚・辛の日には西方で白龍を殺し、壬・癸の日には北方で黒龍を殺すという(占いがある)。」
『春秋繁露』求雨(紀元前2世紀頃)
原文
秋暴巫至九日、無舉火事、家人祠門。為四通之壇於邑西門之外、方九尺、植白繒九。祭之以桐木魚九、玄酒、具清酒、膊脯。衣白衣。以庚辛日為大白龍一、長九丈、居中央。為小龍八、各長四丈五尺、於西方。皆西鄉、其間相去九尺。鰥者九人、皆齊三日、服白衣而舞之。
現代語訳
秋の雨乞いでは、巫女を九日間日晒しにし、火を使うことを禁じ、各家庭では門を祀る。町(邑)の西門の外に、四方に通じる九尺四方の祭壇を作り、九本の白い布(繒)を立てる。供物には桐の木で作った九匹の魚と、玄酒(水)、清酒、干し肉を用いる。参列者は白い衣を着る。庚(かのえ)・辛(かのと)の日には、長さ九丈の大きな白龍を一体作り、中央に配置する。また、長さ四丈五尺の小さな龍を八体作り、西の方角に置く。これらはすべて西を向かせ、それぞれ九尺の間隔をあける。妻を亡くした男(鰥者)九人が三日間の斎戒を行い、白い衣を着てこれを舞わせる。
『淮南子』墬形訓(紀元前2世紀頃)
原文
白金千歲生白龍、白龍入藏生白泉、白泉之埃上為白雲、陰陽相薄為雷、激揚為電、上者就下、流水就通、而合于白海。
現代語訳
白金(しろがね)が千年の時を経ると白龍(はくりゅう)を生じ、白龍が地中に隠れ潜むと白泉(はくせん)が湧き出る。白泉から立ち昇る塵(ちり)は白雲となり、陰陽の気がぶつかり合って雷となり、激しく飛び散って稲妻となる。上にあるものは下へと降り、流れる水は滞りなく通じて、やがて白海(はくかい)へと合流するのである。
『列仙伝』陵陽子明(紀元前1世紀〜2世紀頃)
原文
陵陽子明者、鄉人也、好釣魚於旋溪。釣得白龍、子明懼、解鉤拜而放之。後得白魚、腹中有書、教子明服食之法。子明遂上黃山、采五石脂、沸水而服之。三年、龍來迎去。
現代語訳
陵陽子明(りょうようしめい)は、鄲(たん)の郷里の人である。旋溪(せんけい)で釣りをすることを好んでいた。ある時、白龍を釣り上げたが、子明は恐れおののき、針を外して拝礼してこれを放してやった。その後、一匹の白い魚を釣ると、その腹の中に書物があり、子明に(仙人になるための)服食の法を教えていた。子明はついに黄山に登り、「五石脂」を採って沸騰した水とともに服用した。三年後、龍が彼を迎えに来て、子明は龍に乗って去っていった。
『説苑』正諫(紀元前1世紀頃)
原文
昔白龍下清冷之淵、化為魚、漁者豫且射中其目、白龍上訴天帝、天帝曰:「當是之時、若安置而形?」白龍對曰:「我下清冷之淵化為魚。」天帝曰:「魚固人之所射也;若是、豫且何罪?」
現代語訳
昔、白龍が「清冷の淵」に降り立ち、魚に姿を変えていた。そこへ漁師の豫且(よしょ)が矢を放ち、その目を射抜いた。白龍は天界へ戻って天帝に訴え出たが、天帝はこう尋ねた。「その時、お前はどのような姿をしていたのか?」白龍が「清冷の淵に降りて、魚の姿になっておりました」と答えると、天帝は言った。「魚というのは、もともと人が射る(獲る)ものである。そうであれば、豫且に何の罪があろうか(いや、罪はない)。」
『焦氏易林』(紀元前1世紀頃)
原文
(坤之臨)白龍赤虎、戰鬭俱怒。蚩尤敗走、死於魚口。
(蒙之坎)白龍黑虎、起鬐暴怒。戰於涿鹿、蚩尤敗走。居止不殆、君安其所。
(同人之比)白龍黑虎、起伏俱怒、戰於阪兆;蚩尤走敗、死於魯首。
(益之比)白龍黑虎、起伏俱怒。蚩尤敗走、死於魯首。
現代語訳
白龍と赤虎が、共に怒り狂って戦った。蚩尤は敗れて逃げ出し、最後は魚の口(地名、あるいは文字通り魚の口)で死んだ。
白龍と黒虎が、その背びれを逆立てて激しく怒った。涿鹿(たくろく)の地で戦い、蚩尤は敗走した。これにより人々は危うきを逃れ、君主はその居所に安んじることができた。
白龍と黒虎が、身を躍らせ伏せたりしながら共に怒り、阪兆(はんちょう)の地で戦った。蚩尤は敗走し、魯首(ろしゅ)の地で死んだ。
白龍と黒虎が、身を躍らせ伏せたりしながら共に怒った。蚩尤は敗走し、魯首(ろしゅ)の地で死んだ。
『白山之記』(平安時代末期〜鎌倉時代)
原文
頂上之池(翠ヶ池)有白龍、為神之化身。其形如大蛇、首有角、色如雪。
現代語訳
(白山の)山頂にある池には白龍が住んでおり、神の化身である。その姿は大きな蛇に似て、頭には角があり、色は雪のように白い。
『西遊記』(1592年)
第三十回
原文
那怪變做個俊俏文人入朝、與國王認親、把師父變作老虎。又虧了白龍馬夜現龍身、去尋師父、師父倒不曾尋見、卻遇著那怪在銀安殿飲酒。他變一宮娥、與他巡酒、舞刀、欲乘機而砍、反被他用滿堂紅打傷馬腿。
現代語訳
あの怪物(黄袍怪)は、見目麗しい文人に化けて宮廷に入り込み、王と親戚の契りを結ぶと、師父(三蔵法師)を魔法で虎に変えてしまった。この窮地を救ったのが、夜に龍の正体を現した白龍馬であった。師父を捜しに出たものの見つからず、銀安殿で酒を飲む怪物に遭遇する。白龍馬は宮女に化けて酒を注ぎながら剣舞を披露し、隙を見て斬りかかろうとしたが、逆に怪物が投げた燭台(満堂紅)によって馬の脚を負傷させられてしまった。
第四十回
原文
一時間、風聲暫息、日色光明。行者上前觀看、只見白龍馬戰兢兢發喊聲嘶、行李擔丟在路下、八戒伏於崖下呻吟、沙僧蹲在坡前叫喚。
現代語訳
ひとまず風が止み、日が差し込んできた。行者(悟空)が様子を見に行くと、白龍馬は恐怖に震えながらいななきを上げ、荷物は道に放り出され、八戒は崖下でうめき、沙僧は坂の前で叫んでいた。
第五十二回
原文
又去後面看處、見八戒、沙僧與長老還綑住未解、白龍馬還在槽上、行李擔亦在屋裡。
現代語訳
(怪物が)さらに奥の方を見に行くと、八戒、沙僧、そして長老(三蔵)がまだ縛られたままになっており、白龍馬も飼い葉桶のつながれた場所に居り、荷物も部屋に置かれたままであった。
第六十五回
原文
同八戒、沙僧、(不領唐三藏、丟了白龍馬)各執兵器、一擁而上。
現代語訳
(神々が)八戒や沙僧と共に、各々武器を手にして一斉に襲いかかった。(ただし、唐三蔵は連れ出せず、白龍馬も置き去りにされたままであった。)
第八十回
原文
八戒道:「分了、便你還去流沙河吃人、我去高老莊探親、哥哥去花果山稱聖、白龍馬歸大海成龍。師父已在這妖精洞內成親哩、我們都各安生理去也。」
現代語訳
八戒が言った。「荷物を分けちまえば、お前(沙僧)は流沙河へ戻って人間を食えるし、俺は高老荘へ里帰りできる。兄貴(悟空)は花果山で聖者としてふんぞり返り、白龍馬は大海に帰って本物の龍に戻れるんだ。師父はもう妖怪の洞窟で結婚しちまったんだから、俺たちも各々好きに生きようぜ。」
『三才図会』(1609年)
原文
(鳥獸巻・龍の項目より抜粋) 龍、西海有白龍。……又、白龍、金之精也。
(神祇巻・河伯の項目より抜粋) 河伯、姓馮名夷。……或曰、河伯化為白龍、游於水畔。
現代語訳
(鳥獣巻) 龍について。西海には白龍がいる。……また、白龍とは(五行説における)「金」の精気である。
(神祇巻) 河伯(かはく)は、姓は馮(ふう)、名は夷(い)という。……ある説によれば、河伯は白龍に変化して、水辺を泳ぎ回るという。
『本朝神社考』(1645年)
原文
凡、蛇之白者、人称之曰白龍神。以為水神、或以為福徳神。
現代語訳
およそ、白い蛇は、人々はこれを「白龍神」と呼んで崇める。ある者は水神とし、ある者は福徳(金運・幸運)の神とする。
『和漢三才図会』巻第四十五・龍蛇部(1712年)
「龍」について、『説文解字』では「肉」に従う字形とし、鱗を持つ生き物の長(おさ)であるとされる。「蛇」について、古くは「它」と書き、その身をくねらせて曲がっている形を象ったものである。現在は「虫」を加えて「蛇」と書く。
李時珍が言うには、諸々の蛇は春に出現する。春夏を「昼(活動期)」とし、秋冬を「夜(休眠期)」とする。冬は土を口に含んで穴にこもる。春になって外に出るとその舌を吐き出す。耳は聞こえないが、目で音を聞き取る。とぐろを巻く時は北(壬の方角)を向く。毒はよだれにあり、怒った時は毒が頭と尾に集まる。その珠(たま)は口の中にある。歩く時はくねくねと進み、食べる時は丸呑みにする。牙はあるが歯がないからである。交尾の際はオスがメスの腹に入り、終わればすぐに出ていく。人が蛟(みずち)の交尾を見ると三年のうちに死に、蛇の交尾を見ると吉事があるという。水中では石斑魚(ウグイ等)と交わり、またカメやスッポンをメスとすることもある。山に入ればクジャクやつがいになり、キジとも交わる。「夔(き)は蛇を羨み、蛇はシラミを羨む」という言葉がある。蛇はネズミを呑み込むが、逆にネズミに食われることもある。蛇はカエルを呑み込むが、ガマ(田父)には制圧されてしまう。
蛇が食べる虫は、カエル、ネズミ、スズメ、コウモリ、鳥の雛などである。蛇が食べる草は、セリ、ナス、イシノキ、シュユ、ヘビノゴザ(蛇粟)などである。蛇が嫌う物は、ミョウガ、アンリュウ(植物名)、蛇芮草(ヘビイチゴ)、ガチョウの糞である。恐れる薬は、雄黄、雌黄、羚羊(れいよう)の角、ムカデである。ムカデは大きな蛇を見ても、気(霊力)によって蛇を動けなくさせ、その脳や目を食べる。また、ヒキガエルはムカデを食べ、蛇はヒキガエルを食べるという、物事には互いに恐れる関係がある。誤って萵菜(レタス)に触れると、蛇は目が見えなくなる。
蛇が人の足に巻き付いた時は、熱い尿をかけるか熱湯を注げば自然に解ける。蛇が人の体内の穴(竅)に入り込んだ時は、モグサをその尾に置いて灸を据えるか、尾を切り割って山椒の粉を詰めれば、すぐに出てくる。「蛇には足があるが、それを見るのは不吉だ」と言う者がいるが、桑の木の火で蛇を焙れば足が現れるので、不思議なことではない。また、五月五日に地面を熱く焼いて酒を注ぎ、その上に蛇を置けば足が現れる。
按ずるに、蛇の大きいものを「乎呂知(おろち)」と呼び、また「倍美(へみ)」とも称する(倍美は反鼻、つまりマムシの別名である)。小さな蛇の総称は「久知奈波(くちなわ)」といい、朽ちた縄に似ているという意味である。近年、オランダから蛇の毒を治す薬が伝わっている。「須羅牟加(スラムガ)」という小さな黒い石や、「波布手古不羅(ハフテコフラ)」という樹、「留宇駄(ルウダ)」という草などがある。これらは今では各地にあり、蛇の毒をよく治す。
およそ龍も蛇もくねって進むが、四つの足があるものを「龍の属」とし、手足がないものを「蛇の属」とする。しかし、龍と蛇は本来は同一の種類である。春夏に龍が天へ昇るのを見ることは時折あることだ。ある人が船で琵琶湖を渡り北の浜に着いた時、一尺(約30cm)ほどの子蛇が泳いでくるのを見た。その蛇は芦の梢に登って舞い、水に下りてはまた登るのを数回繰り返すと、みるみるうちに一丈(約3m)ほどの大きさに成長した。これこそが「天行法(天に昇る術)」であろう。すると黒雲が辺りを闇夜のように覆い、車軸のような激しい雨(白雨)が降った。龍が昇天し、わずかに尾が見えたかと思うと、そのまま虚空へと消え、空は再び晴れ渡った。
『造化権輿』には「龍は骨を替え、蛇は皮を替え、鹿は角を替え、蟹はハサミを替える」とある。
『信濃奇勝録』(1834年頃)
この地の古井戸より白蛇現る。村人これを「白龍大権現」と崇め、祠を建てて祈雨の神とする。
『甲子夜話』巻34(19世紀前半)

武雄山の白竜
寛政3年(1791年)の夏、長崎から一人の客が訪ねてきた。ある晩、その人と話をしていると、その客が所蔵している文書に、ある僧が数年前に白竜を見たという話が記されているという。その僧は虚言を語るような人物ではなく、話は真実だと思われた。私はその話を書き留めようとしたが、客は「僧はすでにそのことを書き残しています」と言った。後に、その記録を手に入れた。
白竜観記
私は肥前国の武雄宿に到着した。日もすでに西に傾いていた。
宿に入り温泉に入ってから、気ままに散策した。
宿の西にある山は、高さ百仭(約百数十メートル)ほどもあり、松や杉が青々と茂り、山道は急で険しかった。
山頂では岩が重なり合って立ち並び、奥深く鬱蒼として、人の寄りつかぬような場所であった。
そこで衣を整えて山を下りた。
山の中腹に、左へ折れる細道があり、土地は狭く平らで、切り立った岩壁が並んでいた。
そこに池があり、水は極めて澄み、冷たかった。
同行の者たちはそれぞれ手ですくって飲み、青く澄んだ景色の中を歩き回っていた。
私はひとり池のほとりに立ち止まり、しばらく彼らを待ちながら、水をせき止めて飲んでいた。
すると水中に何かが見え、きらきらと光っていた。よく見ると、それは真っ白な龍であった。
二本の角が競うように立ち、細い毛が頭を覆い、顎にはびっしりとひげが連なっていた。
鱗とたてがみは互いに映え合い、氷や雪よりもなお白く清らかであった。
ただし瞳だけはやや黒く、大豆ほどの大きさであった。
両足を池の底に踏みしめ、首を持ち上げてこちらを正面から見ていた。
顔の長さは七、八寸(約21〜24センチ)、胴回りは両腕で抱えられるほどで、
上半身は二尋(約3メートル)ほど見えていたが、下半身は見えなかった。おそらく岩穴の中に続いていたのであろう。
その姿は激しく恐ろしいものではなく、むしろ端正で気高かった。
これを易の乾卦に当てはめるなら、「九三の乾乾惕若(常に励み、慎み恐れる)」の象であろうか。
私との距離は数尺(約1メートル)ほどで、しばらく向かい合っていた。
私が恐れなかったのは、その姿が荒々しくなかったからであろう。
そこで同行の者たちを呼び、「ここに霊妙なものがいる、来て見るがよい」と言った。
しかし彼らが到着する前に、龍は突然姿を消してしまった。
山を下りて宿に戻り、この出来事を宿の主人に話した。
主人は驚いて言った。「おそらくあの山の神でしょう。あのようなものを見たという話は、まだ聞いたことがありません。」
この出来事は、宝暦13年(1763年)7月21日のことである。
長崎の白竜大寿がこれを記し、書き残した。
私は肥前国の武雄宿に到着した。日もすでに西に傾いていた。
宿に入り温泉に入ってから、気ままに散策した。
宿の西にある山は、高さ百仭(約百数十メートル)ほどもあり、松や杉が青々と茂り、山道は急で険しかった。
山頂では岩が重なり合って立ち並び、奥深く鬱蒼として、人の寄りつかぬような場所であった。
そこで衣を整えて山を下りた。
山の中腹に、左へ折れる細道があり、土地は狭く平らで、切り立った岩壁が並んでいた。
そこに池があり、水は極めて澄み、冷たかった。
同行の者たちはそれぞれ手ですくって飲み、青く澄んだ景色の中を歩き回っていた。
私はひとり池のほとりに立ち止まり、しばらく彼らを待ちながら、水をせき止めて飲んでいた。
すると水中に何かが見え、きらきらと光っていた。よく見ると、それは真っ白な龍であった。
二本の角が競うように立ち、細い毛が頭を覆い、顎にはびっしりとひげが連なっていた。
鱗とたてがみは互いに映え合い、氷や雪よりもなお白く清らかであった。
ただし瞳だけはやや黒く、大豆ほどの大きさであった。
両足を池の底に踏みしめ、首を持ち上げてこちらを正面から見ていた。
顔の長さは七、八寸(約21〜24センチ)、胴回りは両腕で抱えられるほどで、
上半身は二尋(約3メートル)ほど見えていたが、下半身は見えなかった。おそらく岩穴の中に続いていたのであろう。
その姿は激しく恐ろしいものではなく、むしろ端正で気高かった。
これを易の乾卦に当てはめるなら、「九三の乾乾惕若(常に励み、慎み恐れる)」の象であろうか。
私との距離は数尺(約1メートル)ほどで、しばらく向かい合っていた。
私が恐れなかったのは、その姿が荒々しくなかったからであろう。
そこで同行の者たちを呼び、「ここに霊妙なものがいる、来て見るがよい」と言った。
しかし彼らが到着する前に、龍は突然姿を消してしまった。
山を下りて宿に戻り、この出来事を宿の主人に話した。
主人は驚いて言った。「おそらくあの山の神でしょう。あのようなものを見たという話は、まだ聞いたことがありません。」
この出来事は、宝暦13年(1763年)7月21日のことである。
長崎の白竜大寿がこれを記し、書き残した。
スポンサーリンク
|
|