猿神 ― 日本の伝説に登場する猿の妖怪 ―

猿神(さるがみ)とは、日本の説話集や民話に登場する猿の妖怪のこと。
伝説によれば、自らを神と偽って生贄を求めたことから、狩人や犬に退治されたといわれている。
また、同名のものには、神・神使としての猿神 や 憑物としての猿神 が存在する。
基本情報
概要
猿神は人を喰うといわれる猿の妖怪で、平安時代の説話集や日本各地の民話などで伝承されている。
主な説話では「人里に神として祀られており、里を荒らさない代わりに毎年一人の生贄を要求する。生贄には里の娘が選ばれ、親が助けを求めた 人 または 犬 によって倒される」といった内容になっている(詳しくは下記の資料を参照)。
このように物語には一定のパターンがあり、その中で語られる特徴としては「人よりも大きな猿」で「犬(山犬)に弱い」といった点が挙げられる(犬猿の仲を象徴するように犬が登場するパターンが多い)。
こうした説話においては、猿神の細かい特徴を描いた説話は少ないが、狒々(ヒヒ)という大猿の説話に類似するものが多いことから、狒々と同一もしくは同様の特徴を持つものという見方もできる(狒々に特徴を記した資料は多い)。
また、猿神と呼ばれるものとして、 山の神やその神使としての猿神や、中国・四国地方で伝承される憑物としての猿神も存在する。ちなみにインドにはハヌマーンなどの猿の姿をした神もいる。
神・神使としての猿神
神や神使として信仰される猿神としては、山王信仰における日吉神の使いの神猿や、庚申信仰における青面金剛の使いの三猿などが有名で、地域によっては山の神として信仰されることもあるといわれている。
また、『日本現報善悪霊異記』には、近江国にある三上山に住む僧の前に猿が現れて「自分はインドの王だったが、生前の罪で猿に生まれ変わり、この神社の神となった」と語ったという話もあるという。
ちなみに、日本では鬼門とされる丑寅(うしとら)の方角に対して、裏鬼門の未申(ひつじさる)を当てると魔除けになると信じられたことから、京都御所の猿ヶ辻のように丑寅(北東)の方角に猿が祀られていることも多い。
憑物としての猿神
日本の民間伝承には憑物としての猿神がいるといわれ、その起源について「昔、頭は猿、胴は犬、尾は蛇の鵺(ヌエ)という怪物がおり、退治された時にそれぞれの部位が各地に落ち、頭は猿神、胴は犬神、尾は蛇神となった」という話がある。
憑物としての猿神に関する話は少ないが、岡山県や徳島県あたりでは犬神に並ぶ憑物として伝えられており、憑かれた人は暴れたり 発狂したりするといわれている。
また、『今昔物語集』に登場する美作国(現・岡山県)の猿神は、宮司に憑依して自分の意志を伝えたとされることから、妖怪として伝えられている猿神と同じものなのかも知れない。
データ
| 種 別 | 日本妖怪 |
|---|---|
| 資 料 | 『今昔物語集』『宇治拾遺物語』など |
| 年 代 | 平安時代? |
| 備 考 | 同名のものに神や憑物がある |
類似する妖怪
狒々 ― 人を見て笑う大猿の怪物 ―
狒々(ひひ)とは、日本や中国の山奥に棲息していたとされる大猿のこと。 大きな上唇を持ち、人を見て笑うという特徴があり、狒々の名は その笑い声に由来するといわれている。
資料
文献
『今昔物語集』巻二十六第七 作國神依猟師謀止生贄語
今は昔、美作国(現・岡山県)に中山と高野という神社があり、中山の神は猿、高野の神は蛇の姿をしているという。年に一度の祭の日には国人の未婚の娘を生贄を捧げる決まりがあり、この風習は古くから今まで決して止むことはなかった。
ある時、この国に16,17歳になる清楚で美しい娘がいた。父母は娘に愛情を注いで育てていたが、今年 娘が生贄に捧げられることになったため、できることなら身代わりになりたいと思うほど悲しんだ。しかし、これより一年間は娘を肥やして祭りの日に生贄に立てるという決まりになっている。そのため、父母は決まりに逆らうことはできず、過ぎ去る日々を悲しみ、只々涙を流すことしかできなかった。
そんな時、縁あって東方より美作国にやって来た狩人がいた。この狩人は多くの飼犬を連れており、山に入って猪・鹿を獲る"犬山"という仕事を生業としており、心が極めて強く、物怖じしない性格であった。
狩人が国に滞在している間、自然と生贄の話も耳に入ってきた。そこで、生贄に選ばれた娘を持つ家に事情を聞きに行こうと思い、その家の蔀(しとみ)から中を覗いてみると、そこには 色白で長い髪を垂らした 田舎娘とは思えぬ とても美しい娘がいた。狩人は この娘は泣き伏せる姿を見て、とても哀れで愛おしく思った。
そこで親に会って事情を聞くと、親は「これは昔からの風習なので仕方がないことだ。だが、一人娘を生贄に立てる日が近づくにつれて悲しみも増してくる。前世になにかの罪を犯して生まれてきたのだろうか」などというので、狩人は「世に生きる人の命に増さる物はない。それに一人の娘がいたずらに殺される必要があるだろうか?神仏であろうと娘の命を救えるならば怖くはない、この娘を私にくれないか?そうするならば、私が娘の身代わりになろう」と答えた。
それを聞いた親は「では、何からすればよいでしょうか?」と尋ねると、狩人は「では、精進潔斎するといって家に注連縄を張り、外から家内を見えないようにして欲しい」と言った。すると、親は「娘が死なないのであれば、私達も苦しまずに済みます」と言って狩人の提案を受け入れ、こっそり狩人と娘を合わせて婚姻を結ばせて、しばらく共に暮らした。
狩人は娘と暮らしているうちに命が惜しくなったので、犬山の中から2頭の猛犬を選りすぐって「お前たちは私の代わりだ」と言い聞かせて、山から密かに生まれたての猿の子を獲らせてきて、人の居ないところで これを喰わせて"猿は敵だ"と教え込んだ。なお、犬と猿は元々仲が悪いと言われるので、見ればすぐに攻めかかって殺す。
狩人は このように犬を訓練するとともに、自分の刀を丁寧に磨いで戦の準備をしていた。そして、妻に「私はお前の身代わりになって死ぬかもしれない、これが別れになると思うと悲しい」と言うと、妻も同じく哀しく思った。
祭りの当日がやってくると、宮司をはじめ多くの人々が神社に集まって生贄を迎えに来た。そこで新しい長櫃を持ってきて「生贄をこれに入れよ」と言うので、狩人は狩衣・袴許を着て、刀を握りしめ、長櫃の中に入り、その脇には2頭の猛犬を忍ばせた。また、このとき親には娘を入れたよう見せるよう指示した。
そして、鉾・榊・鈴・鏡を持つ者らが行列を為し、その先を長櫃が運ばれて行った。娘は「何事もありませんように」と恐れる一方、身代わりになった狩人を哀れに思い、親も「娘が生贄に出されるという苦しみは去ったが、これもまた同じように苦しい」と思った。
行列が神社に到着すると、瑞籬の戸が開けられて長櫃が運び置かれた。そこで、宮司が祝詞を上げると、長櫃に結ばれた緒が切られ、祝詞が終わると共に瑞籬の戸が閉められて、人々は外に出ていった。
しばらくして狩人が長櫃のフタを開けてみると、そこには体長2メートル以上の大猿が横に座っていた。なお、歯は白くて、顔と尻は赤い。また、次々に猿が現れて やがて100以上並んだ。その面は赤く、眉を上げて叫んでいる。また、猿の前には まな板と大刀が置かれており、酢塩や酒塩といった調味料も用意され、まるで鹿を料理するような状態であった。
そして、大猿が長櫃に手を伸ばすと、他の猿どもも立ち上がって、フタを開けるほどに興奮している。そこで、狩人はにわかに隙間を作って犬に「喰らいつけ」と命じると、2頭の猛犬が飛び出して大猿に喰らいついた。
大猿が倒れると、狩人は凍ったように鋭く磨いだ刀を抜き、大猿をまな板に押し当て、その頭に刀を突き立てながら「お前らが人を殺して食い続けるならば、この首を切り離して犬に喰わせてやる」と言うと、大猿は顔を赤らめながら、涙を流し、手をすり合わせて命乞いした。
だが、狩人はそれを聞き入れずに「お前は来年以降も多くの人の子を生贄に欲するだろうから、今ここで殺してやる。もし、お前が神ならば、私を殺してみせよ」と言って、頭に刃を添えた。なお、その間に2頭の犬は他の猿を噛み殺していたが、生き残った猿は木に上って山にいる仲間の猿を呼び集めるので、埒が明かなかった。
しばらくして、一人の宮司が憑かれたように「我は今日より先、永遠に生贄を求めず、人々の命を奪わず、生贄の女や父母・親類にも害をなさない。故に早まるな、我を助けよ」と言ったので、宮司らが皆 社に集まって「神はこのように申している。どうか許してやってほしい」と狩人に頼んだ。
しかし、狩人は許そうとせずに「私は命が惜しいのではない。多くの人の命の代わりに これを殺すのだ」と言うので、宮司は祝詞を上げて大猿に誓いを立てさせると、狩人も許して放すことにした。すると、大猿はすぐさま山に逃げ出していった。
そして、狩人は家に帰って妻とともに末永く暮らし、生贄を立てる悪習もなくなったという。
※『宇治拾遺物語』巻第十にも同様の説話が載っている
『今昔物語集』巻二十六第八 飛騨国猿神止生贄語 第八
今は昔、仏道修行をして各地を行脚する僧がいた。
僧はやがて飛騨国に到ったが、そこから山奥に進むにつれ、道も分からなくなるような険しい山道に入ってしまった。人里を求めてひたすら歩き続けたが、道らしい道もなくなり、やがてすだれのようにかかった大きな滝が落ちる高く広い場所に出た。
そこから引き返そうとしても道が分からず、進もうとしても登れそうにない断崖絶壁が続くばかりで、為す術がなくなったので、仏に救いを求めて念じていると、後方から人の足音が聞こえてきた。
振り返ってみると、そこには蓑笠をまとい、荷物を背負った男が歩いてきたので、人に逢えたことを嬉しく思い、道を尋ねようと近づいていくと、僧を見た男はひどく怪しんだ様子で避けようとする。だが、後がない僧は思い切って男に道を尋ねてみると、男は何も答えないまま、滝に方に歩いて行き、そのまま滝の中に入ってしまった。
僧は あの男はきっと鬼だったのだろうと思って怖気づいたが、このままでは埒が明かないので、仏に後生の救いを祈り、思い切って男のように滝の中に飛び込んだ。すると、溺れ死ぬだろうと思っていたのに、不思議と顔に水をかけられた程度で滝を通り抜けることができ、その内側に道を発見した。
僧が道を進んでいくと、やがて人里に辿り着き、その先には多くの人家も見えた。助かったと思った僧は、人家に向かって歩いていくと、先程の荷物を背負った男が荷物を置いてこちらに走ってくる。また、その後ろから浅黄色の着物の男がやってきて僧の手を掴んだ。
僧が驚いていると、浅黄色の着物の男は「どうぞ、我が家においでください」と言い、この他にも大勢の人々が集めって僧を家に迎えようとする。すると、次第に口論が始まり、その中の誰かが「郡司殿の所に連れて行って、この男の所有を決めよう」などと言い出し、結局わけの分からないまま とある大きな家に連れて行かれることになった。
その大きな家には長老らしき翁がおり、人々に連れてきた理由を尋ねると、荷物を背負った男が「この人は、私が日本国から連れてきて、この人に差し上げたのです」と浅黄色の着物の男を指さしたので、翁は「ならば、そなたの物ということになる」と言って、浅黄色の着物の男の所有を認めた。これに他の者も納得し、方々に去っていった。
僧は「彼らはきっと鬼で、自分を喰うつもりなのだろう」と思って涙をこぼした。また、僧は先程の問答について「なぜ、彼は日本を何処か遠い国のようにいったのだろうか」と疑問を抱いた。そのとき、浅黄色の着物の男が「そんな怪訝な顔をしなさるな。ここは楽しい世界です。あなたには豊かな生活をしてもらおうと思っているので、ご心配なく」と言った。
そして、案内されるままに浅黄色の男の家に着いた。その家は郡司の家よりは小さかったが、立派な造りで、男女の使用人が大勢いた。また、家の者達は喜んで待っていたかのように大騒ぎしている。
浅黄色の男は僧を板敷の間に迎えると、早速食事の用意をさせた。しばらくすると、魚や鳥が見事に調理されて出てきたが、僧が食べようとしなかったので、浅黄色の男がなぜ食べないのか問うと、僧は「私は幼くして法師になりましたので、いまだかつてこのような物を食べたことがありません。ですから眺めていたのです」と答えた。
すると、浅黄色の男は「なるほど、ごもっともなことです。ですが、私の客人であります故、召し上がってもらわないワケにはいきません。私には可愛がっている一人娘がいますが、未だに独身で、そろそろ年頃なので貴方の妻にしていただこうと思っています。ですから、今日から髪を伸ばしください。伸ばせば外に行く必要もありますまい」などと言う。
僧は逆らえばきっと殺されるだろうと思って怖気づき、浅黄色の男の言うことに従うことにした。また、僧侶の身であったため、食事に箸をつける前に「仏はどのように思し召しになるだろうか」と考えたが、結局料理を平らげてしまった。
その後の夜、20歳くらいの美しい女性がきれいに着飾った姿で僧の前に現れ、主人(浅黄色の男)が「この娘を差し上げます。今日からは貴方が可愛がってください。たった一人の娘なので、私の愛情のほどを察してください」と言うので、僧は修業のことなど忘れ去って、その娘を抱き寄せた。
こうして、僧と娘は夫婦となって月日を過ごすことになり、その日々は例えようがないほどに楽しかった。衣食住の不自由はなく、好きな物を好きなだけ食べられるので、僧が別人のように太ってしまった。また、髪ももとどりを結えるほどに伸びたので、髪を結い上げられるようになり、常に一緒に暮らす相思相愛の仲で、8ヶ月ほどの月日が過ぎた。
ところが、その頃からこの妻の顔色が変わり、大層 物思いにふけっている様子になった。だが、主人は以前に増して世話してくれるようになり、もっと太ったほうが良いと言って、日に何度も食事を用意させたので、僧はさらに肥えた。
だが、僧が肥えるにつれて、妻は声を殺して泣くようになり、僧がその理由を尋ねても詳しく答えようとしなかった。それでも泣く日々が増えるので、僧は怪しんだが、理由を聞ける人間もいなかったので そのままにしていた。
ある日、家に客がやって来て主人と話をしていた。僧がそっと立ち聞きしてみると、客人は「うまい具合に人を手に入れましたな。さぞかし嬉しいことでしょう」と言うと、主人は「そうですよ、あの人を手に入れられなかったら、今頃はどんな気持ちでいることやら…」などと言っている。
客人が帰ると、主人は使用人を呼んで僧のための食事を用意せよと命じるので、いつものように食事を摂りながら、今までのことを振り返ってみると、なんとも恐ろしい予感がしたので、改めて妻に理由を問うたが教えてもらえなかった。
そうこうしている間に、周りでは里人が忙しそうに何かの準備をしている様子が目に写った。各家は饗応のお膳などの準備に追われて大騒ぎしている。僧は我慢できなくなって、妻に「お前は私には隠し事をしないと思っていたが、このように隠し事をし続けるなど何とも情けない」と言って涙を流すと、妻は泣きながら「隠そうなどとは思っていませんが、顔を見たり話をする時間が残り少ないと思いますと、このように睦まじくなったことが悔やまれるのです」と答えた。
そこで、僧は「それは私が死ななければならないということなのか?死はどんな人にもやがて訪れることなので、どうということはない。ただ、それ以外のことがあるならば、どういう事なのか教えて欲しい」と頼んだ。
僧の思いに応えた妻は、泣きながら「この国には、大変恐ろしいことがあります。国の霊験を示される神様は、人を生贄として食べるのです。貴方がここに来た時に皆が家に迎えようとしたのは、この生贄に当てようと思ったからなのです。毎年一人ずつ、順に生贄を出すのですが、その生贄を手に入れることが出来ない時には、愛しいわが子でもその生贄に出すのです。もし貴方が来なかったら、この私が生贄となって神様に食べられたと思いますと、むしろ私が替わってあげたいと思うほど苦しいのです」と言った。
そこで僧は妻を慰め、神の生贄がどのように調理されて供えられるのか尋ねると、妻は「生贄を裸にしてまな板に寝かせ、玉垣の中に担ぎ込まれて、人々が去った後に神は調理して食べてしまうと言われています。そのときに、生贄が痩せていると、神は怒って作物は不作になり、人々は病んで、里が荒れてしまうので、このように何度も食事させて、太らせるのです」と答えた。
また、僧は神の姿について妻に尋ねると、それは猿の姿をしているという。そこで、僧は妻によく鍛えられた刀を用意するように頼むと、妻は一振りの刀を手渡してくれたので、僧はそれを隠し持って、暇があれば何度も磨いで切れ味を整えていた。今までの経緯を理解した僧は、これまでの堕落を払拭するかのように気力に満ち溢れ、食事を進んで摂ってさらに肥えたので、主人をはじめ、里人たちも皆 喜んだ。
そして、生贄に出す7日前になると、家には注連縄が張られ、僧は精進潔斎するように言われた。また、他の家にも注連縄が張られて、慎ましい雰囲気となった。妻はあと数日で夫が居なくなると思うと悲しみを堪えられずに泣くことも多かったが、生贄となる僧が平然としているので、多少は心が安らいでいた。
いよいよ生贄となる当日になると、僧は沐浴させられ、衣装や頭髪もきちんと整えられた。準備ができると主人とともに馬に乗って出かけ、やがて山中にある神殿に着いた。その神殿(宝倉)は大きく、周りには玉垣が巡らせてある。また、神殿の前には馳走を盛った膳がたくさん置かれていて、その様子を大勢の人が見守っている。
僧は その饗応の席の一段高いところに座らされて食事を与えられる。また、他の者達も皆で飲食し始め、舞を舞ったりして楽しんだ後に、僧を裸にして、髪をほどき、絶対に動かず、口を利かないよう 言い聞かせてまな板に寝かせ、その四隅に榊を立てて注連縄や御幣を縣け廻らせると、まな板を担いで玉垣の中に置き、扉を閉めて去っていった。このとき僧は股の間に刀を挟んで隠し持っていた。
やがて一の宝倉の扉が開けられると、僧は全身の毛が逆立つほど恐怖した。すると、他の宝倉の扉も次々に開けられていき、しばらくして人間ほどの大きさの猿が現れた。次いで、一の宝倉のすだれを押し開けて出てくるものが現れ、見てみれば それはさらに一回り大きな猿で、歯が銀を連ねたようで、堂々とした態度であった。しかし、神の正体を見た僧は「所詮は猿だったな」と思うと気が楽になった。
こうして集まった猿どもは、鳴き声を発して互いに意志を確認すると、僧の方に歩み寄ってきて、用意された長い箸と刀で切ろうととしてきたので、僧は咄嗟に隠し持った刀を取って素速く立ち上がり、目の前の猿に斬りかかった。すると、猿は驚いて倒れたので、僧は踏みつけて「お前が神か」と問うと、猿は手をすり合わせて命乞いをした。また、その間に他の猿は一目散に逃げ、木の上から威勢よく鳴き声を発していた。
そこで、僧は傍にあった葛をちぎって猿を柱に縛り付け、その腹に刃を突き立てると「猿であるお前が神などと偽り、毎年人を喰うなど全くけしからん。お前の第二、第三の御子だと言っていた猿をここに呼び出せ、さもなくば突き殺すぞ。もし、お前が神であれば刀は通用しないだろうが、それを今から試すこともできるのだ」と言って、少しばかりえぐるマネをすると、猿は叫びながら命乞いをするとので、僧は「さぁ、早く呼び出せ」と命じた。
すると、猿は僧の支持に従って鳴き声を発し、第二、第三の御子なる猿を呼びつけた。僧はそれらの猿も柱に縛り付けると「お前たちがこれから言うことを聞くなら命だけは助けてやろう。今日より後、もし事情も知れぬ人を祟ったり、人に危害を加えようとするならば、その時にはお前たちを残らず始末してやる」と言って、玉垣の内の猿どもを皆 木の根元に縛り付け、祭りの残り火を取って、宝倉に火を点けて廻った。
なお、この社は人里離れた場所にあるので このことを知る者はいなかったが、里から社の方角に火の手が上がっているのが見えるので、里人は何事かと怪しんで騒然とした。しかし、祭りの日から3日間は家の門を閉ざして外出しない決まりになっていたので、現場に駆けつけようとする者は誰も居なかった。
また、僧を送り出した主人は何か騒ぎが起こっていることで祟りがないか不安に思っていたが、妻は僧が刀を隠し持っていたことを知っていたので、きっと彼が起こしたことなのだろうと思っていた。
しばらくすると、裸体に葛の蔓で帯刀し、ざんばらの髪を振り乱した姿の僧が、捕らえた4匹ばかりの猿を追い立てて、杖を突きながら里に下りてきた。これを見た里人たちは「神の御子が捕らえられているとはどういうことか?我々は神にも勝る者を生贄に出してしまったのか、では我々はこのまま喰われてしまうのか…」などと思って恐怖した。
そして、僧は妻と主人の住む家に向かい「門を開けよ」と叫んだ。しかし物音さえしないので「決して悪いことなどしていないので心配することはない、だが、開けなければかえって悪いことになるぞ」と言って門を蹴り立てた。すると、恐れた主人は娘に「彼は自分に復讐するつもりなのかもしれない、門を開けてどうかうまくなだめてくれ」と頼んだ。
妻は恐ろしく思う反面、夫の無事を喜び、門を細めに開けると、僧は門を押し開けて「早く部屋に戻って、私の装束を取ってきてくれないか」と言った。妻は急いで部屋に戻り、狩衣・袴・烏帽子などを持ってきたので、捕らえた猿どもを家の戸口に縛り付けた後に着替えて、家にあった武具を身に着けて主人を呼び出した。
主人が来ると、僧は「この猿どもが神の正体です。こいつは猿丸といって、人に飼われればいじめられるばかりのものだが、こんなものに長年 行きた人を喰わせていたというのは実に愚かなことです。私がここにいる限り、このものどもにひどい目に遭わされることはなくなるでしょう。全て私にお任せ下さい」と言って、猿の耳をキツくつねった。
この話を聞いた主人は僧が頼もしく思えて「私達は今まで こういったことを全く知りませんでした。今後は貴方を神と仰ぎ奉って、この身をお任せいたします。何事も仰せのままに」と言ったので、僧は郡司に事情を話すことを提案し、主人と猿どもを連れて、郡司の家に向かっていった。
郡司の家に着き、門を叩いたが開けようとしないので、主人が「申し上げることがありますので、早く門を開けて下さい。開けないとかえって悪いことになりますよ」と脅すと、郡司は恐る恐る門を開けた。そして、生贄に出した僧に対して深く土下座をした。
そこで僧は、連れられてきた猿に対して「長年の間 神と偽って人を食ってきた お前たちは、悔い改めよ」と叱り、持ってきた弓矢で猿を射ようとすると、猿は叫び声を上げて手をすり合わせながら命乞いをした。また、これを見た郡司は主人に近寄って「まさか、私も殺す気なのか…どうかお助けくだされ」と言うと、主人は「安心してください、私がついているからには、そのようなことにはなりますまい」と その場を諌めた。
また、僧は猿に向かって「よしよし、お前たちの命までは取らないでおこう。ただし、これから先に辺りをうろついて人に危害を加えるならば、その時は必ず射殺してしまうぞ」と言って、杖で20回ばかり猿を叩いた。この後、僧は里人を集めて社に向かわせ、焼け残った宝倉を全て壊させ、一箇所に集めて焼き払わせた。その上で叱った猿どもを里から追放すると、猿は足を引きずりながら山深くに逃げ去り、以後、姿を現さなくなった。
なお、この僧は後に村の長者となり、里人たちを統制して美しい妻と睦まじく暮らした。また、僧は他国に行くこともあったので、その時にこの話が伝えられたのだろう。
不思議なことに国には、元は馬・牛・犬がいなかったが、猿が去ってからはそれらが増えていった。また、飛騨国の近くにこのような場所があるとは聞いていたが、信濃国の人も、美濃国の人も行ったことはなく、向こうから人が来ることはあっても、こちらから行くことはできなかったのである。
思うに、かの僧が この里に迷い込み、生贄を止めさせ、後に長者となったのは みな前世の因縁であろう…などと伝えられている。
『藤袋の草子』
近江国(現・滋賀県)で老人が畑を耕しつつ「サルでもいいから、仕事を手伝ってくれた者を自分の婿にしよう」と呟くと、大猿が現れて畑仕事を手伝いはじめ、「約束は守ってもらうぞ」と念を押して立ち去って行った。
その翌日、老人の家に大猿が現れて、娘を藤で編んだ袋に閉じ込めて山へ連れ帰ってしまった。老人は狩人に救いを求めると、狩人は大猿が娘のもとを離れる隙を見計らって救い出し、娘の代わりに犬を入れておいた。
そこで、戻ってきた大猿が袋を開けると、中に入っていた犬に噛み殺されてしまった。また、老人の娘は救ってくれた狩人と結婚したという。
民間伝承
山王社の人身御供
昔々、七尾の山王社には毎年のように美しい娘を人身御供に出すという慣わしがあった。人身御供を出す家の屋根には白羽の矢が立つので、これを合図に その年の生贄が決まる。そして村祭に日に生贄として捧げられることになるという。
よって、今年も白羽の矢が某家の屋根に立つことになった。そこで、その家の父は娘をなんとか助け出そうと思い、色々考えた挙げ句、祭りの前に宮に忍び込んで、生贄を欲する神の正体を探ることにした。
その夜の丑三つ時、社殿に何者かが現れて「そろそろ娘を喰らう祭りの日だが、越後のシュケンは我が能登に潜んでいることは知るまい」と呟いているのが聞こえた。そこで、父はそのシュケンを手掛かりに越後に向かうことにした。
父は越後でシュケンを尋ねて方々を周り、ようやく手掛かりを得て訪ねてみると、それは全身を真っ白い毛に覆われたオオカミであった。
父が事情を話して助けを求めると、シュケンは深くうなずき「随分前に他国から3匹の猿神が渡ってきて、人々に害をなしたので、そのうち2匹は噛み殺してやった。残る1匹は姿を暗ましたが、能登に居たとは夢にも思わなかった。それでは今から向かって退治することにしよう」と言って、父を背に乗せて波の上を駆け抜け、翌日の夕方には七尾に到着した。
祭りの当日、シュケンは娘の代わりに唐櫃の中に潜み、その夜に村人によって神前に供えられた。その日は暴風雨であったが、猿神とシュケンの格闘する音は物凄く、社殿にヒビが入るほどであった。
翌朝、村の人々が恐る恐る社殿を見に行くと、血に染まった1匹の大猿が横たわっており、シュケンもまた冷たくなって倒れていた。そこで人々はシュケンに感謝し、手厚く葬ることにした。
また、後難を恐れて、人身御供の代わりに3匹の猿神に因んだ3台の山車を山王社に奉納することにしたという。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
|
|
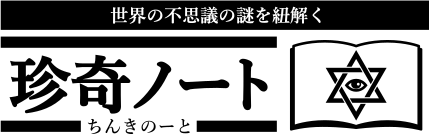
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿