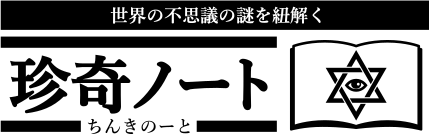戸隠山の鬼伝説
スポンサーリンク
『太平記(直冬上洛事付鬼丸鬼切事)』
足利高経は合戦における忠孝が他の一文の人々と比べて群を抜いているため、将軍(足利尊氏)も恩賞を他の誰よりも重く扱っていた。そのため、何事に不満を持っているのか理解に苦しむが、今 突然に敵に寝返って将軍の世を傾けようとするのはなぜなのか、その恨みの元を調べてみると次のようなことが原因であった。
何年か前の越前の足羽における合戦の時、この高経は朝敵の大将である新田義貞を討ち取り、源平累代の貴重な宝物である「鬼丸」「鬼切」という二振りの太刀を手に入れたのだが、将軍が使者を通じて「この刀は源氏一族の中でも末端の者が手にするべきではない。すぐに引き渡せ。当家の家宝として嫡流の者が相続していくことにする」と度々申し入れていたものの、高経は惜しんで「これら二振りの太刀は長崎の道場に預けておいたのですが、道場が火災に遭った時に焼けてしまいました」と言って、同じ寸法の太刀にすり替えて「焼け損じた太刀です」と提出した。
ところが この事情が京都に伝わり、将軍は大変憤慨した。朝敵の大将を討ち取った忠孝は抜群であったが、それほどの恩賞を与えることもせず、事あるごとに不名誉な扱いをすることが多かったので、高経はこれを根に持ち、足利直義が謀反を起こした時も直義の味方をし、今回の直冬の上洛においても彼に協力して攻め上ることになったのである。
そもそも この「鬼丸」という太刀は、北条時政が天下を取って国内を安定させてから、身長一尺ばかりの小さな鬼が夜な夜な時政の枕元に来て、夢か幻か分からないが苦しめられることが度々あった。修験道の行者に加持祈祷してもらったが効果はなく、また陰陽寮によって退治を試みるも立ち去ることはなかった。このためか時政は病気になり、心身ともに苦しめられた。
ある夜、時政の夢の中で太刀が一人の老翁に姿を変えて「私は常に汝を擁護するため、あの妖怪を退治しようとするのだが、汚れた人間の手によって剣を握られたことにより錆びてしまい抜こうにも抜くことができない。早々にあの妖怪を退治したいなら、心清浄なる人に我の錆を拭き取ってもらうように」と言うと、老翁は再び太刀の姿に変わった。
時政は目覚めると老翁が教えた通りに、ある侍を水で清めさせて太刀の錆を拭き取らせ、鞘には入れずに寝室の傍らの柱に立て掛けた。冬場であったので部屋を温めようと、火鉢を近くに取り寄せて火鉢を置いた台を見ると身の丈1尺(約30cm)ばかりの小鬼が施されており、それは銀で鋳造されたもので、目には水晶が入り、歯には金を沈められていた。時政は夜な夜な自分を悩ませる小鬼はこれに似たものだったと思っていると、急に立て掛けた太刀が倒れて小鬼の頭を削り落とした。すると、その瞬間に時政の気分は晴れ、それからは小鬼の夢も見ることは無くなったという。
そして この太刀は「鬼丸」と名付けられ、北条高時の代に至るまで肌身離さず守り神として平氏の嫡流家に伝わってきたのである。高時が鎌倉の東勝寺で自害した時に、この太刀は次男の時行に家宝として渡され、祝部を頼って信濃国に落ちのびさせた。建武2年(1335年)8月、中先代の乱において時行は鎌倉の合戦に敗れ、諏訪三河守をはじめ、主立った大名40余人が勝長寿院の大御堂の中に走り込み、顔の皮を剥いで自害したが、その中にこの太刀があったので、きっと時行もここで切腹したのだろうと人々は皆で哀れんだ。そして、この太刀は勝者の新田義貞に渡ったのである。
太刀を手にした義貞は大いに喜び「これは平家代々に伝わる有名な"鬼丸"という貴重な宝物だ」と言って秘蔵してきた。そもそも、この太刀は奥州宮城郡の国府にいた三の真国という刀鍛冶が3年かけて精進潔斎し、七重に注連縄を張って鍛えた刀である。
また、「鬼切」というのは、もともとは清和源氏の先祖である源頼光の太刀であった。その昔、大和国の宇陀郡に大きな森があった。この森陰に夜な夜な怪しい者が現れ、往来する者を捕まえて喰ったり、牛馬六畜を捕まえて引き裂いて喰っていた。頼光はこの話を聞いて、家来の渡辺綱という武士にその怪しい者を討つように命じると、秘蔵の太刀を与えた。
綱は早速 宇陀郡に向かい、甲冑で身を固めて毎晩その森陰で待っていた。しかし、怪しい化物は綱の威勢に怖気づいたのか、いつまで経っても姿を現さなかった。そこで、綱は変装して騙してやろうと、髪の毛をかき乱して頭を覆い、髪飾りを付け、歯を黒く染め、眉も太く描き、薄衣を纏うなどの女装をし、朧月夜の明け方に森の近くを歩いていた。
すると、突然 空が暗くなり、森の上方に何かが立ち上ったように見えたかと思うと、空中から綱の髪を掴んで宙に持ち上げる者があった。そこで、綱は頼光から賜った太刀を抜き、虚空を切り払うように太刀を振るうと、雲の上で叫び声が聞こえたかと思うと、その血潮が顔にかかり、黒い毛に覆われて爪の曲がった三本指の腕が、肘の部分から切り取られて落ちてきた。その後、この腕は頼光に渡された。
頼光は腕を朱色の唐櫃の中に収めて置いたが、それからというもの、毎晩のように恐ろしい悪夢を見るようになったので、占夢の博士に占わせてみたところ、7日間の厳しい謹慎をするべしとのことだった。そこで、頼光が屋敷の門を固く閉ざし、七重に注連縄を張り、4つの門には12人の当直を決めて、毎夜宿直の者に蟇目(音の鳴る矢)を射させた。
謹慎の7日間になろうとする夜、河内国の高安の里より頼光の母君がやって来て屋敷の門を叩いた。物忌で謹慎の最中であったが、自分の母が遠路遥々面会にやって来たということで断ることもできずに中に入れることにした。そこで、綱らを呼んで終夜にわたって酒宴を開くと、頼光は酔って気持ちが和らかになり、綱が斬り落とした化物の腕の話を母に聞かせると、母はどんなものか見たいと言うので、頼光は唐櫃を開けて腕を取り出し、それを母の前に置いた。
母はその腕を手にとってしばらく眺める素振りを見せたが、肘から先の無い自分の右手を差し出して「これは自分の手じゃ」と言って自らの肘に添えると、突然身の丈2丈(6.06m)ほどの牛鬼に姿を変え、酌をしようと立ち上がっていた綱を左手で吊り上げながら頼光に飛びかかった。そこで、頼光は例の太刀を抜いて牛鬼の頭をいとも簡単に斬り落とした。
すると、牛鬼の首は空中に飛び上がり、太刀の刃の部分を五寸食い切り、口に含んだまま半時ばかり飛び跳ねながら吠え騒いでいたが、やがて力尽きて地上に落ちて絶命した。それでもなお、胴体は屋敷の破風を突き破って飛び出し、遙か上空に上って行ったという。今に至るまで、渡辺党の者が家を建てる時に破風を取り入れないのはこれが由縁である。
その頃、苦行を重ねて煩悩から解かれた横川の僧都・覚蓮を招き、壇の上にこの太刀を立て、注連縄を張って7日間の祈祷を行ったところ、刃が欠けた太刀に天上から倶利迦羅竜王が下りてきて、太刀の峰を口に含んだところ、刃の部分は元通りになったという。
その後、この太刀は多田満仲(源満仲)の手に渡り、信濃国の戸隠山で鬼を切ったことがある。これらの理由から この太刀を「鬼切」というのである。この太刀は、伯耆国の会見郡の大原安綱という刀鍛冶が精神統一し、あらゆる煩悩を捨てて、一心不乱に鍛えに鍛えた剣である。
その当時、この刀は征夷大将軍の坂上田村麻呂に献上された。田村麻呂将軍が鈴鹿御前と鈴鹿山で決闘した際に使用された刀である。その後、田村麻呂が伊勢大神宮に参詣した際、朝廷から夢の告げに従うようにいわれ、この太刀を伊勢大神宮に奉納した。また、後に源頼光が伊勢大神宮に参詣した時に、夢に神仏が現れて「汝にこの太刀を授ける。子々孫々にわたって嫡流に伝え、天下の安定を護るように」と示現のあった太刀である。こういう事情があるので源氏が保管して相続していくのも当然のことである。
金平浄瑠璃『六孫王経元』
天暦2年8月15日、名月が2つ出ると異常なことが起こるというが、占いによれば北方の月が滅びたのは平将門の怨霊が原因で、これによって帝が病に罹るという。そこで、六孫王経元が三田左衛門延綱(渡辺綱の父)を従えて北方の月を弓で射らせると、鬼形を現して大地に落ちたので、延綱が首を打とうとしたが、たちまち天に飛び上がって行方知れずになった。しかし、帝の病も治ったので経元は褒美に源氏の姓を賜ることになった。
その後、諸国の侍たちは六孫王経元が源氏の姓を賜ったことを聞きつけ、奉公しようと経元の屋敷に挨拶に集まった。この時、経元は少々具合が悪かったので嫡子の満仲に応対させると、侍たちは各々が千秋万歳の御喜を申し上げたのだが、そこに居た信濃国人の望月左近の大夫有茂という者が「この度、経元公が魔王を退治になられたことは天晴弓矢の誉でございますが、満仲殿は御子息であられますから、ご自身でも変化の物を討たなければ世の人の嘲りを受けることになりましょう。幸い我が国の戸隠山には鬼神が棲んでいて、里人や牛馬を襲うので、農民や木樵は自分の仕事を捨てて逃げ出し、国は日ごとに衰えています。どうか満仲殿に下向していただき、この鬼神を退治して欲しいのです」と言った。
すると、満仲は顔色を変えて「いかに有茂、汝の言葉は耳障りだ。良いか、武将の家を継ぐ者が変化を討たなければ人々に嘲りを受けるとは どの軍書にも書いてはいない。父の経元は帝の玉体を悩ます悪魔を退治したが、化物がいなければ武士の頭になれないと申すのか。その上、国の仇を代わりに討てとは何とも都合の良い話だ。帝の勅命を待つか、そうでなければ己で考えて鎮圧すべきであろう。お前の考えで私に討てと指図するのは何とも怪しい話であり、尚且無礼であろう。どうだ」と言った。
これに有茂はしまったという様子で、地に頭を付けて赤面していた。このとき、坂田源太金末が満仲の後ろに控えていたが、元より我慢の効かない男だったので、話に割って入って「どうだ望月、ものを知らなければ教えよう。かの侍の忠信は謀反を企てて国家を傾けようとする者を直ちに言上し、もし大事なことをぐずぐずしていたら、大変なことになると申し上げるのが本文である。どうして悪魔や変化の物などを討ち取る必要があろうか。信濃国に居ながら自分自身の手で鬼神を討ちもせず、お上に申し出るのは侍の恥である。自身の恥辱もわきまえずに出てきて、利口顔に御主君の満仲様にお討になってくださいなどと気の利いたような考えを申すことこそ大笑いである。お前がいうような事だから、それは定めて狐狸の化けたものだろう。お前のような大臆病者は侍の内に入れるのも穢らわしい。早々に立ち去るが良い。どうでも一言口答えするのであれば、殿が、などという必要もない。この金末が微塵にしてくれようぞ。どうだ」と言った。
これを聞いた満仲は「よしよし。あの程度の侍は心のほどもそんなものであろう。この度は、ここにお出かけの方々の手前もあるので許そう」と言って席を立つと、一座の人々も安堵して有茂を引っ張って宿所に帰っていった。
その後、満仲は金末を呼び「望月の言うことは、たとえ彼は身分賤しい者で、わきまえがなく言ったことではあるが、私が若い身で鬼神を討てといわれて、討たないでそのままにしておくならば、理屈の善し悪しは別として臆病者といわれてしまっては悔しいことだ。よって密かに私とお前で戸隠山に行き、鬼神を討とうと思うがどうだ」と言うと、これに金末も了承した。これは話の善し悪しにかかわらず、御供せよというから「ごもっとも」と申し上げるのである。
満仲は満足して「それならば密かに出かけよう」と旅支度して、金末一人を連れ立って信濃路を目指して進むとほどなく野原に出た。そこで「いざ、諏訪明神に願を掛けよう」と神前で鰐口を打ち鳴らし、「南無や諏訪大明神、戸隠山の鬼神を討せたまえ」と深く祈ると、その夜はそこに籠もることにした。
夜半頃のこと、諏訪大明神は80歳ばかりの老人に姿を変え、松尾の神に一領の緋縅の鎧を持たせ、満仲の枕元に置き「これ満仲、この鎧はかつて利仁将軍が東国の賊を討つ間、この宝殿に納め置いた鎧である。只今、お前に与える この鎧を身に着けて戸隠山に分け入り、鬼神を討つならば、問題なくして上手くいくことだろう。また我はお前の行末を守ってやろう」といって消えるように居なくなった。満仲は起き上がると感謝を述べて虚空に三度伏し拝み、すでに夜明けだったので そのまま出立した。
満仲が明神から賜った鎧と「鉄丸」という剣を身に着けると、金末も武装して戦の準備を整えた。そして、主従二人で戸隠山に分け入ったが、いくら探しても有茂の言うような鬼は見当たらなかった。よって、さらに奥へと分け入ると、やがて大きな岩穴が見つかった。そこで、満仲は穴の脇に立って「さあ鬼神よ よく聞け、我を誰だと思う、清和天皇が孫、六孫王の嫡子、満仲とは私のことであるぞ。どうあがいても逃さぬから尋常に出てまいれ。どうだ、どうだ」と言うと、周囲の草木が振動して、そこに身の丈一丈(3.03m)ほどの鬼神が岩穴から現れた。
鬼神は満仲目掛けて一噛みしようと飛びかかったが、満仲は体をかわして斬りかかった。斬られた鬼神は逃げ出したが、そこを金末が逃すまいと追いかけ、そのまま取っ組み合いとなったが、力は鬼神の方が勝っていたので金末は逆に取り押さえられてしまった。そこに満仲が走り寄って鬼神の首を鮮やかに打ち落とし、金末を引き起こして鬼の首を持たせた。こうして満仲は晴れて都に凱旋すると、皆は満仲の御手柄を讃えて感心しないことはなかったという。
一夜山の鬼伝説
天武13年(684年)、天武天皇が信濃国に遷都しようと計画し、調査のために三野王や采女臣築羅らを派遣した。水無瀬という土地に棲む鬼たちはこれを邪魔しようと一夜で山を築いたので、怒った天武天皇は官軍を派遣して鬼たちを尽く討伐してしまった。そのため、水無瀬は「鬼無里(きなさ)」と呼ばれるようになったという。
『とがくし山(戸隠山絵巻)』
神武天皇以来、44代を経て国を治める帝を元正天皇という。この帝が古代中国の三皇五帝を慕って信心に励み、賢臣の諌めを用いて佞臣を退けた。これによって善に近づき悪を離れたからであろうか、国は豊かに治まり、民は安穏に暮らしていた。このため、国土の人民はもとより波を隔てた遠国に至るまで、帝になびかない草木も無かったのである。
すると、治安の良い御代の徴であろうか、美濃国から不思議な奏聞があった。というのも、本栖郡に泉が湧き出て、この水を飲めば 白髪の者は黒髪に、老いた者は若返り、若者はいつになっても年を取らないということである。このことを土地の住人が都に申し上げたところ、殿上人も奇異に思って急いで帝に申し上げると、帝は「このような不思議な事は今まで無かった。急いで勅使を遣わせて見てまいれ」との勅命を下した。
これにより勅使が派遣され、事の様子を見に行ってみると、まことに世にも稀な不思議な有様であった。勅使が辺りの里人に事の詳細を尋ねると、里人は「この泉がいつ湧き出したのかは分かりませんが、私は老いた父を養うために山に入って薪を切っており、休憩の折に泉を見つけてなんとなしに飲んでみたところ、疲れが取れ、心身共に若返りました。ですので、水を持って急ぎ帰って父に与えると、白髪は黒髪になり、足も軽く、寝起きも良くなって、疲れがなくなったということです。それで朝夕欠かさず水を飲み続けましたら、いつしか自分も年を取ることがなくなりました。こうしたわけで飲み始めた人々も この不思議を知ったのです」と答えた。
話を聞いた勅使も自ら泉を訪れ、その様子を調べた後に都に帰って帝に奏聞した。これに帝も大いに関心し、すぐに年号を養老と改めた。まことに聖代の御代には、このような瑞相(めでたい事の前兆となるできごと)がある。漢朝にもその例が多い。よって、帝も政を怠ることなく、君も臣も安穏に過ごしていた。
こうして、年月を過ぎていくうちに、また人々が煩うことが出てきた。というのは、東山道の信濃国の戸隠山に不思議な変化の者(鬼神)が棲み着いて、最初は日暮れに動いていたので人と出くわすことも少なかったが、後に昼夜問わず鬼神の姿を現すようになり、麓に居りてきては、往来するものを苦しめたという。このため、関東からの貢物を都に送ることができず、都から東に向かうのも困難になった。また、近隣の住民は鬼神に襲われて殺された者もいるということで、次第に田畑を耕すことがなくなり、昼夜通して家に閉じこもるようになった。
そこで信濃国の人々は皆で集って「昔もこのような事があったが、このままにしておけば土地の者は悉く鬼神に滅ぼされてしまうだろう。生き残っていても家から出られないのならば将来も不安である。こうなったら都に訴えて、信濃国に平安を取り戻そうではないか」と相談し、向かう者を数十人集めて都に向かわせたのであった。
こうして一行が都に着くと、早速 事の次第を帝に訴えた。すると、帝は大層驚いて信濃国の者にさらに詳しく事情を聞くと、帝は殿上人を集めて その対策を相談させた。そこで堀川内大臣が「昔もこうした例があります。天智天皇の御代にも、藤原千方という逆臣が鬼を従えて召使っていましたが、宣旨を頂いて改めるとたちまち滅びたという例があります。今もそうでしょうから、急いで武士に命じられて退治されてはどうでしょうか」と進言すると、帝は納得してその適任となる者を問うた。すると、内大臣は「吉備大臣(きびのおとど)という者は文武二道ですので、この者に命じられるのがよろしいでしょう」と申し上げたので、早速 吉備大臣のもとに勅使が遣わされた。
勅使から話を聞いた吉備大臣は驚いてすぐに参内すると、帝は「信濃国の戸隠山に鬼神が棲み着き、国中の人々を悩ませている。よってお前は急いで信濃に下ってこの鬼神を退治せよ」と勅命を下した。吉備大臣は了承したものの「私のような者が一人で行っても退治するのは難しいでしょう。そこで天下に名の通った者を遣わせたほうが良いのではないでしょうか」と申し上げたところ、公卿や殿上人が「お前の申すことも尤もであるが、数多の者の中からお前が選ばれたことこそ面目である。その上、このような帝のお言葉は倫言汗の如くであるから、すぐに向かわねばならぬ」と言った。これに吉備大臣は「重ねて申し上げることは勅諚に背くことになるので、そう言われるのであればすぐに向かいましょう」と言って出ていった。
吉備大臣は宿屋に帰ると、郎党の蘇我河麿と紀貞雄という大剛の者を召して「お前達よく聞け、今 信濃国の戸隠山には鬼神が棲んで人々を悩ませて困窮を招いているという。そこで我らに鬼神退治の勅命が下ったのだ。よって明日には信濃に下ることになる。汝ら二人は共に付いてまいれ」と言った。二人は了承し「これは大事だが、数多の者の中から我が主人に勅諚が下った家の誉である。たとえ鬼神が神通力を持っていても目さえ見えれば滅ぼすことができよう。その上、勅諚があるのだから、いよいよ頼もしく思われる」などと言って喜んだ。
吉備大臣は「お前達が言うように勅諚を持っていくのであれば少しも心配することはないが、ここは神仏の力を借りるべきだろう。我は長年 長谷の観音を信仰してきた。参籠したいと思うもが、今はその時間が無い。早く出かけよう」といって、長谷の観音に使者を送った。養老2年9月中旬、吉備大臣は河麿と貞雄を大将として総勢50余騎を引き連れ、信濃国の者3人に道案内させて都を出発し、やがて大津の浦に辿り着いた。
そこから瀬田の橋を渡り、野路の篠原を過ぎ、夜も進んで急ぎ行き、とうとう信濃国に着いた。案内の3人は、まず大臣一行を民家で休ませた。大臣は夜明けに戸隠山に分け入ろうと提案し、3人の案内人を呼んで山の様子を尋ねたところ、3人は「あの山は越中の立山、加賀の白山に続きますが、なかなか険しく鳥でなくては通いようもありません。老木が茂って月や日の光も届かず、木の葉が積もってまともな道も無いので、たまたま往来した者が迷ってしまうこともあります」などと説明した。これを聞いた大臣は「いずれにせよ、山に向かって見なければ様子も分からない。そこで、もし鬼神と出くわしたならば、こちらの思い通りに退治してやろう」と言って、その夜は床に就いた。
夜が明けると一行は戸隠山に分け入り、そのまま進んでいくうちに、山の端は白くなり、横雲が棚引き、日の光も次第に差してきたので、大臣は「人が多くて思うように進めない。河麿・貞雄の二人だけ着いてこい。残りの者は麓で待て。人が多ければ鬼神も恐れて出てこないだろうから、お前達は出てきた時の用意をしておけ」と命じた。
吉備大臣は、真新しく照り輝く緋縅の鎧、赤地の錦の直垂を着け、二尺八寸の太刀を佩き、上に薄衣を一つ打ちかけて戸隠山に分け入り、河麿も萌葱糸縅の鎧に褐色の直垂を着け、貞雄も小桜縅の鎧を着けて後を追った。残りの者どもは、麓の野辺に留まり、そこで鬼を捕らえようと気張って待ち受けることにした。
こうして3人で戸隠山を進んでいくと、案内人に聞いた通りに凄まじい場所で、9月の下旬ともあった峰には木枯らしが吹き、木の葉が積もって道も無い。山路には霞が深く、日の光も稀に指す程度なので時刻も分からなかった。このような不気味で険しい所を過ぎると やがて穏やかな場所に出たので、3人はここで休憩することにした。
そこで吉備大臣が「ようやくここまで来て夕日も沈んでしまったが、未だに鬼は見つからない。されは宣旨を畏れたか、または観音の仏力で我らの威勢を恐れたか、誠に不思議なことだ」と言うと、二人は「誠におっしゃる通りです。ですが、いずれにしても鬼を見つけるまでは山を降りるわけにはいかないでしょう」と申し上げた。これに吉備大臣は「よく言った、俺もそれは心得ている。この山で暮らすことになろうとも鬼の姿を見ずに故郷に帰ることはできまい」と言い、持参した乾飯などを食べながら飢えを凌いだ。
すると、峰の方から人の声が聞こえたので、大臣は不思議に思って「これこそ例の鬼であろう、さあ行くぞ」と言って、山奥に分け入っていくと、そこには美しい女房が2人居て涙を流していた。大臣は「これはきっと変化の者だろう。我々を騙そうとして女に化けて出てきたのだ。お前たちはあやつらを連れてまいれ」と言うと、河麿が女のもとに近づいて行ったが、女は恥ずかしげに木陰に隠れてしまった。
河麿が「お前たちは何者だ。なぜこのような人気の無い山に居るのだ。怪しいぞ」と言うと、女房は「私たちはこの山の者ではありません。麓の者です」と答えた。これを聞いた河麿は帰って大臣に報告すると、今度は大臣自ら近づいて「お前たちはよく聞け、この山には鬼が棲むと聞くが、それが何処であるか教えよ」と言った。すると、女房は涙を流しながら「左様でございます。ですが、私たちは存じません。この峰の向こうに気高い上臈が大勢で酒盛りしていらっしゃいます。彼らこそよく知っておられるでしょう。私たちは鬼の棲んでいる所に入ったことはありません。ですので、酒盛りの所に行って尋ねてください」と答えた。
大臣は この女房たちも一緒に連れて行くことにし、また峰を遥々と越えて行くと、聞いていた通りに気高い女房が6,7人で酒宴をしているようだった。そこに大臣が立ち寄ると、女房たちは恥ずかしげな様子で木陰や岩陰に隠れたので、大臣が「皆様方、どうかされましたか、私は怪しいものではありません。どうして隠れるのですか、早く出てきて下さい」と言うと、女房たちが恥ずかしげに出てきて「お姿をお見受けしますに都の人かと存じます。私たちはこの山の者ではありませんが、わけあってこのような深山に来て、誰にも知られずに遊んでいました。そこに突然あなた方が現れたので、恥ずかしくなって隠れてしまったのです」と答えた。
大臣は「恥じられることはありません。一樹の陰の宿りにも他生の縁と聞いております。このような時に言葉を交わすのも前世からの縁でしょう。我らは都の者で東に下ってきたのですが、道に迷ってここまで来てしまったのです。どうか帰り道を教えて下さい」と尋ねると、女房は「都の人と聞けば懐かしく感じます。ならばこちらへおいで下さい。道をお教えしましょう。ですが、この一河の流れを汲む酒を見捨てて行くのも気が引けます。ですので、どうぞどうぞ」と言って酒を勧めてくる。
大臣たちも人間なので心弱くも立ち寄って、紅葉の見える風情を楽しみながら酒宴に加わると、やがて女房たちと打ち解けた。そこで大臣は「どうか皆様お聞き下さい。この山には鬼が棲むと聞きましたが本当でしょうか。もし知っているのであれば何処にいるのかお教えください」と尋ねると、女房たちは「左様でございます。この山には九生大王(くしょうだいおう)という、身の丈1丈(3.03m)あまりの鬼が棲んでおります。その眷属も相当の腕を持つ者ばかりです。今は陸奥国に行っているので2,3日は帰らないでしょうから、私達は鬼の居ぬ間にこうして心を慰めているのです」と言い、打ち解け顔で酒を強いるので、大臣たちは盃を受けては酒を飲み、やがて前後不覚になるほど酔ってしまった。
大臣たちが辺りの岩を枕に微睡んでいると、女房たちはしてやったりと喜び、皆 本性の鬼の姿を現して「急ぎ九生大王に伝えよ」といって鬼の窟に戻っていった。こうして大臣たちは知らぬ間に窮地に追い込まれたが、そこに長谷の観音が現れて「大臣よ、何をしておるのだ。このような宣旨を承ったのに大事の敵に気づかず、かような不覚をとろうとするのか、さあ早く起きよ」と言い、かき消すように消え失せてしまった。
ここで大臣は目覚め、辺りを見渡してみても女房たちの姿は無い。また家来の二人も野原に伏している。そこで大臣は声を張り上げて二人を起こすと、二人も目覚めて四方を見渡し、どういうことかと不思議がる。大臣は「不思議なことだ。先程の女房たちはこの山の鬼だぞ。戦の用意をせよ」と言い、薄衣を脱ぎ捨てて、太刀を抜き、三人で身を寄せ合って大木を盾にしながら鬼が現れるのを待っていた。その時の心境はとても頼もしいものだった。
そうこうしているうちに、例の女房たちは鬼の姿を現して窟に戻り、九生大王の前に出て「大臣たちを騙してたっぷり酒を飲ませてやりました。今頃は酔っ払って寝ているでしょう。急いでお出になられて、さっさと餌食にするのが良いでしょう」と言うと、大王は大いに喜び、眷属どもを引き連れて大臣の居る場所に向かったが、そこには大臣の姿が無かった。これに大王たちは慌てふためいて、そこら中を探し回っていると、三人はその様子を見て「おう、鬼が出てきたぞ、一人も打ち漏らすな」と言って身構えた。
そして木陰から姿を現して大声で「おい、鬼ども、しかと聞け。普天の下卒土の中、王土に非ずという事無し。それに何だ、汝は王地を犯すのみならず、往来する者をも悩ませる。その天罰は遁れられまい」と言って、一斉に打ちかかると、鬼どもも「何、王土を犯すだと、昔はそうだったかも知れぬが今は違う。手並みの程を見せてやろう」と言い、皆で三人を取り囲んで攻めた。
両方とも相当な手並みだったので、力比べではなかなか勝負がつかなかった。そこで大王は通力を以って悪風を吹かせたり、火を放ったり、谷や峰を駆けて岩を崩したり、古木を倒して攻めるので、三人は手出しのしようが無くなって窮地に追い込まれた。しかし、帝の威光により、どこからともなく17,18歳くらいの一人の天童が飛んできて、鉄の楯を手に三人の前に立ち、大王の攻撃を防いでくれた。大臣が「かたじけない、されは神仏の擁護であろうか」と言い、三人は奮起して戦い続けたので、飛行自在の鬼どもも、たちまち通力を失って尽く討たれてしまった。
この様子を見て激怒した大王は「憎い奴らめ、さあ俺の手並みの程を見せてやろう」と言って、小高い岩上に飛び乗り、大臣を睨んで立ったのだが、その様子は身の毛もよだつものであった。三人は力を合わせて隙間なく斬りかかると、流石の大王も敵わぬと思ったのか、宙に浮き大臣だけを狙って飛びかかり、組み合ったと思うと険しい山中を上下になって転がっていった。これを見た二人は鬼に向かって休み無く斬りかかると、鬼が少し弱ったように見えたので、そのまま押さえつけて首を斬り落とした。すると、鬼の首は虚空に飛び上がり、口から火焔を吐き出して三人に吐き懸けた。この火焔は防ぎようもなく、鎧の袖を頭に被って木陰を求めて逃げ回っていると、どこからか鷲と能鷹が飛んできて、宙に浮いている鬼の首を続けざまに蹴りつけてたので、鬼の首は深谷の底に堕ちて微塵に砕けてしまった。
三人はかたじけなく思い、手を合わせて拝みながら「今はもう、目的の鬼を滅ぼした。もう心掛かりはない」といって、木陰に立ち寄って休憩すると、やがて日が落ちて暗くなってきた。山路には月明かりも届かないため帰り道も見えず「今宵はこの山で夜を明かそう」と言って、木の葉を集めて焚火を起こし、長い夜寒を明かした。
一方、麓で待っていた残りの者どもは「どうなさったのだろうか、心配だ。さあ探しに行ってみよう」と言って、道も見えない険しい山中を進み、三人を探し回った。そうこうしているうちに夜が明けてきたので、三人は鬼の首を2つばかり持ち帰ろうとしたが、貞雄が「今はもう目的の鬼は滅ぼしたので気にかかることもない。いっそのこと鬼の住処を見に行って故郷の土産話としよう」と提案すると、大臣も納得したので、また山奥に入って鬼の住処を探しに行った。しかし、いくら探しても そのような場所は見つからない。
三人は谷を下って行ったところ、そこに大きな岩穴があったので立ち寄って見ると、入口は石を畳んで門のようになっているが、その奥はどうなっているのか見えない数千丈はある深い谷になっている。藤の蔓を伝って出入りしていたと思われる藤葛がたくさんある。入ってみる必要もないので、大臣が「もう帰ろう」と言うと、二人も了承して帰ることにした。
谷を下り峰を登るうちに帰り道が分からなくなり、あちこち散策してみるも、行く先々は岩石が転がっているばかりである。困った三人は天を仰いで悩むばかりだった。そこで大臣は「知らない山路で迷ってときは、谷に従って出れば必ず里があるという。さあ、谷の水を辿って行こう」と言うので、谷の流れに沿って山を出ようとした。
一方で、大臣たちを探しに山に入った者どもが大声で「この辺りに吉備大臣はおりませんか。蘇我河麿と紀貞雄はおりませんか」と叫んでいた。この声が谷を進む三人にかすかに聞こえたので、大臣は不思議に思って耳を済ませると、どうやら自分たちの名を呼んでいるようなので、きっと麓で待たせた者どもが探しに来たのだろうと思い、すぐに谷から大声で答えた。大勢の者どもは大臣の声を聞いて、すぐに声の方向に探しに向かった。大臣たちが合流すると、者どもは鬼の首を見つけて大喜びし、道案内しながら勇んで麓に出ていった。
信濃国の里人は、この報告を聞くやいなや大臣たちの活躍に感謝して、総出で大臣を拝んだ。大臣はすぐに都に使者を出そうと、御内の者を一人呼び寄せて「良いか、お前は急ぎ都に上って事の次第を詳しく申し上げよ、私は明日にでも上がろうと思う」と言い、自分は民家に入ってしばらく休憩した。
一方、都では大臣が信濃国に下ってから、毎日人を出して大津・粟津・松本の辺りで御迎えしていたが、大臣の御使も程なく瀬田の橋に着いたので、その御迎えに対面した。そこで御使が事の次第を尽く語ったので、御迎えの人々は都に帰ってその報告をした。帝も大臣の活躍を聞いてとても御喜びになり、迎えを出すように言いつけると、殿上人はめでたいことだと我も我もと出迎え、大臣の御台所も思い思いに出迎えた。都から、大津、松本、粟津、瀬田、野路の篠原まで、馬、車、徒歩、裸足の人々は引きも切らない。都の人々はこれを聞き「さあ末代までの物語に見物しよう」といって見物に出て、逢坂辺りは桟敷が並べられていた。
一方、大臣は少しでも早く帰ろうと翌日には信濃国を出立すると、里人たちは大臣に感謝して皆で御見送りをした。こうして大臣は近江国の安川で御迎の人に会うと、皆が馬から降りて大臣に挨拶した。そして、大臣たちが大層な様子で都に凱旋すると、道中の御迎えからそれぞれ挨拶があり、宿所に入ると帝より「参内せよ」との命令があったので、大臣は河麿と貞雄のそれぞれに鬼の首を持たせて帝に参内した。そこで帝より「この度の忠孝は全くもって例えようもない。近くに参って戸隠山での出来事を話せ」と言われたので、大臣は畏まって近くに寄り「女房に酒を無理強いさせられたこと」「鬼の首が宙に飛び回ったこと」「鬼の住処を訪ねたこと」「道に迷ったこと」などを詳しく申し上げると、帝も臣下も驚いて大いに感心した。そして、帝は「誠に並ぶ者のない手柄である」と言って、ただちに大臣に信濃国を与え、その上に御剣や様々な巻物などを取り添えて与えた。また河麿と貞雄は少将に任じられたので、大臣は帝に感謝を述べて宿所に帰っていった。
大臣は「この度の忠孝が成せたのも、長谷の観音の守護があってこそのことだろう。早速参籠しよう」と言って、二人の少将を引き連れて観音に参籠し、33度の礼拝を奉り、それから堂塔を一字も残らず建立した。88間の回廊、44間の廊下、仏前の道具をすべて金銀で磨き調えた。これらは末世の今もそのままで世に珍しいことである。
この後、大臣は急いで戻ると、二人の少将に「この度のお前たちの忠孝は数える暇さえない。その恩賞を受けるが良い」と言って、信濃国の総政所に任じた。二人は感謝して御前を下がり、信濃国に下った。信濃の国中の人々はこれを聞いて「この国が平穏無事であるのも、ひとえにこの方々のお陰である」と言い、様々な果物や貢物を持って、少将殿の下に参上した。
二人は人々を前にして「この度、この国の鬼を従えたこと、これも一つは帝のお陰である。また神仏の力でもある。全くもって人間の力だけでできることではない、しかし勅諚を頂いたからであろうか、思い通りに鬼を滅ぼすことができた。方々も勅諚あるならば、必ず畏れ憚りなされよ。こうした変化の者までも勅諚の前には滅びるものであるぞ」と語れば、国の人々は帝を畏まり、皆 御暇を賜って自分たちの家に帰っていった。
この後、二人の少将は、思いのままに家を構えて栄華に栄えた。こうしたことで大臣は信濃国に下っても益無しということで、都に住み続けた。また、帝は二つの鬼の首を見てどうしようかと思ったが、このような者は末代まで語り伝えるべしということで、七条河原に獄門に懸けて晒されたのであった。
スポンサーリンク
|
|