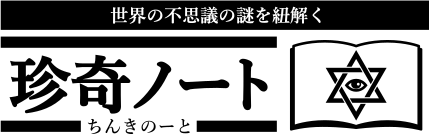貧乏神の資料
スポンサーリンク
『百物語評判』
ある人が言うには…
河西あたりに極めて貧しい者がおり、来る年も侘しく、明くる年も心配が多かった。どうしたものかと身の置き場を案じ、どこで暮らそうかと悩んでいた。そんな時、肩の上に5寸(約15cm)ばかりなるものが落ちてきたので、それを取り上げてみると小さな人形で、目・鼻・口・舌なんかも一通り揃っていた。
その貧者は驚いて「お前は何者だ?なぜ肩に落ちてきた?」と言うと、その人形は「我は世にいう貧乏神で、本日より この身に住まわせて貰うことにした」と答えた。
そこで、貧者は喜んで妻子を呼んで「おい、嬉しいことがあったぞ。本日よりこの者が私に付いたというので、お前たちを辛い目に遭わせてきたが、これからは違って毎度のように贅沢できるぞ。だから、これを打ち殺したり、捨ててはいけない。見つけたら、そのまま助けてやるように」と言った。
これに貧乏神は笑って「お喜びはもっともだが、私はそなたの身を離れることはない。この身の頭から爪先まで諸方の貧乏神が付きまとうだろう。よって、新たな敷神どもも遠方より集って来るのだ。居所が無くなれば誤って落ちることもあるが」と言った。
これに貧者は興ざめして呆れ果てたという。
この神について先生に問うてみると、先生はこのように答えた。
この神は窮鬼という名で、人の貧富は天命の稟受の厚薄によるものといわれるが、聖賢君子のように徳義正しく智慮深い者であろうとも、どうすることもできないという。
しかし、愚かなものは強く貧を嫌い富を求むが、そうすることでその身を下し、名を辱め、後には刑戮に落ちる。こうした類の者は、天命を知らずに幸を願うが故にこうする。常体の者は、天命の説が難しければ仏家にいわゆる三世の説を立てる。そうすると過去の宿業があったとしても害には至らない。
この天運によれば神があって司るなどともいわれるが、唐の韓退と申す大儒も、正月晦日に船を用意して、酒や肉と文章一篇を乗せて、窮鬼を送り出したという。一生の間に不幸が続く故、宗の陳簡斎という詩人の詩にも「韓愈推究究不去 楽天待冨々不来」と作ったとか。
また、宗の范文正公という者は宗朝一人の人品であり、学問・才芸に長けていて好んで人に施した。そのため、後に饒州の守護職になり、家は富んで一門も栄えたという。
しかし、この共に極めて貧しい浪人がおり、渡世の手立ても無かったので、旧友の范文正公を頼ろうと思い、遥か遠くの饒州の范文正公を尋ねてこれを歎いた。范文正公は元より物を惜しまぬ性格であったが、太守といえど一銭の蓄えも無かったので「この夏の税で麦が数万石納められる。そこでお前にこれを売りに出す仕事を与えよう。お前はその金で生活すればよい」と言った。
すると浪人は子息の元に帰って「麦を売る仕事を得たので、お前たちは故郷を通った時に親類の貧しい者に残らず与えて帰れ」と言った。これに范文正公やその友人らも力を落とした。
その後、范文正公は「この州に普の王義の石碑がある。この石摺を売れば一枚あたり黄金一斤にはなるので、これを売るが良い。しかし、平民はこれを売ることはできない」と言って、その石摺百枚を写すための紙と硯を与え、さらに写すべき日についても その近辺に仰せ付けた。
その翌日、范文正公は諸共にそこに出向くと、そこに土民どもが集まっていて「昨日の夕立で落雷があって、それで石碑が微塵に砕けてしまった」と言っていたので、石摺を写すことも出来ずに帰っていったという。云々。
『日本永代蔵(祈る印の神の折敷)』
「掛け奉る御宝前」と書かれた大絵馬が京都の清水寺に掛かっているが、これは呉服所の何某が銀百貫目を祈り、その願いが成就したので、これに名を記して懸けられたと語られている。今、その家の繁盛を以前と見比べば、一代で金銀も貯まるものだと、室町では評判である。人は皆 欲を持つ世であるので、若恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天に頼みをかけ、鉦の緒に取り付ついて元手を願うが、世間が賢い時代になったので、この事は叶い難い。
ここに桔梗屋という元手が僅かな染物屋の夫婦がおり、世渡りを大事にして正直に振る舞って片時も暇なく稼いでいたが、毎年のように、餅つきは遅く、肴掛のブリも無い有様で、新春を迎えることを悔やんでいた。そこで、宝船を枕に敷いて寝たり、節分に大豆を「福は内」と打ったりしたが、その甲斐も無く貧しいことに変わりはなかった。
よって、桔梗屋は貧しさから分別を変えて「世の中では富貴の神仏を祀るのが習わしである。しかし、私は人の嫌がる貧乏神を祀ってやろう」と言い、おかしな藁人形を作り、それに渋帷子を着せ、頭には紙子頭巾を被らせ、手に破れた団扇を持たせた。そして、その見苦しい有様を松飾りの中に置き、元旦から七草の日まで精一杯の饗しをした。
すると、貧乏神は嬉しさのあまりに、その夜に枕元に出てきて「私は長年 貧しい家を巡る役なので、身を隠して様々な哀しい家の借銭の中に埋もれており、悪さをする子供を叱っても『貧乏神め』とあてつけを言われる。また、財力がある家では、絶え間なく銀貨を秤にかける音が響くので癇の虫が起こり、朝夕には鴨鱠・杉焼といった料理が胸につかえて迷惑に思う。私は元来その家に住み着いてまわる神であるから、奥の寝室に入っていると重ね布団・釣夜着・綿の枕が身にこそばゆく、真っ白な寝巻に留められる香りに鼻を塞ぎ、花見・芝居に行っても天鵞絨窓の乗物に揺られて、目眩がするのも嫌である。また、夜は蝋燭の光が金襖に反射するのも気に食わない。貧しい家の灯は、十年も張り替えられない行灯で薄暗いものが良い。夜中に油をきらして、女房の髪の油を間に合わせに注すなど、そのような不自由な有様を見るのが好きで、毎年暮らしてきた。誰も訪ねる者が無く、投げやりにされて、私は貧しさから起こって益々衰微させていたが、この春にお前が心を込めて貧乏神を祀ってくれたので、折敷に食物を置かれるなど前代未聞で初めてである。この恩賞を忘れることはできない。この家に伝わる貧銭を二代目の奢った長者に譲って、忽ちお前たちを繁盛させてやろう。生業には様々なものがある。柳は緑、花は紅」と、2,3度、4,5度と繰り返したので、桔梗屋は目覚めても霊夢を忘れることは無かった。
桔梗屋は有り難いと思いつつも「私は染物細工なので、紅との御告はまさしく紅染のことだろう。しかし、これは小紅屋が大分仕込んで世間の需要を満たしている。それだけではなく、近年の砂糖染の考案や、重い智恵者の京であるので、並大抵のことでは利益を得ることなど思いも寄らない」と考えたが、工夫に明け暮れて考案したところ、蘇芳木の下染を酢で蒸し返すと、本紅の色に変らない事が分かった。そこで、これを秘密にして染め込み、自ら江戸に降って本町の呉服屋に売っては、京に上って材料である奥州の絹綿を仕入れた。こうして差す手、引く手に油断なく商いを続けると、十年もしないうちに千貫目分の財力を持つ家になった。
桔梗屋は、やがて数多の手代を置いて諸事をさばかせるようになり、その身は楽しみを極め、若い時分の辛労を取り返した。これこそ人間の身の持ちようである。たとえ万貫目持っていたとしても、老後までその身を使って気をこしらえて世渡りする人は、一生は夢のように儚いことを知らず、いくら貯めても何の益も無い。
ところで、その家業のことだが、武士も大名もそれぞれが世襲をするので出世を願うことはない。末端の侍は親の位牌・知行を受け取って楽々と生活することは本意ではない。自ら奉公を勤め、官位と俸禄を昇進させることこそ出世である。町人も親に儲けを貯めさせて、遺言状にて家督を受け取り、親が残した商売で、または家賃や貸銀の利息を計って勿体無く世で生活し、二十歳前後から無用の竹杖をつき、置頭巾や長柄の笠を見に付けて、世間の目も構わずに不相応に贅沢する男は、いかに自ら金銀を使っているとしても天命を知ることはない。人は十三歳まではわきまえなく、それから二十四,五歳までは親の指図を受け、その後は自ら世で稼ぎ、四十五歳までに一生の家を固め、有楽することに極まっている。どうしても若隠居などと言って男盛りに勤めを止め、大勢の家来に暇を出し、他の主人に仕えさせれば、末を頼んだ甲斐もなく難儀に遭うことだろう。町人の出世は下々の面倒を見て、その家の暖簾を分けることこそ親方の道である。
総じて三人口までを「身過ぎ」とは言わない。五人から「世を渡る」と言うのである。下人が一人もつかない者は世帯持ちとは言わないのである。「旦那」と呼ぶ人もなく、朝夕の飯も通い、盆なしに手から手に取って、女房盛りで食うなど、いかに腹が膨れようとも残念なことなのである。同じ世渡りでも格別の違いがある。金銀は廻り持ち、念力に任せて貯まるものではない。桔梗屋は夫婦だけで働きだし、今や75人の主人となり、大屋敷の願いのままに七つの内蔵・九間の座敷、様々な草木の他にも銀の生る名木が蔓延っていて、その屋敷は長者の町にあったという。
『譚海』
私の叔父が壮年の頃、昼寝の夢で「破れた衣を纏った乞食のような老人が座敷に入ってきて、そのまま二階に上がっていく」という光景を見た。すると、それ以来は いつも金欠で情けない日々を過ごすようになった。
それから4年を経た時、また昼寝の夢に以前に見た老人が出てきて、二階から座敷に降りてきて暇を乞い、立ち去り際に「ワシは貧乏神である。4年前に この家に来て今から出ていくところだが、ワシが出た後は焼き飯に焼き味噌を少しこしらえよ。それを折敷に乗せて裏の戸口から持って出て近くの川に流すと良い。それから今後は決して焼き味噌をこしらえてはならない。貧乏神は焼き味噌が大好物だからである。しかし、生味噌はもっと悪いぞ。これは味噌を焼く火の気さえ無いと知れるからな」と教えて去っていった。
そこで貧乏神の教えた通りに焼き飯と焼き味噌を作って川に流したところ、それ以後は叔父はさほど金に困らなくなったという。なので、この話を不思議なことだと言って話している。
『耳嚢(貧窮神の事)』
近頃、牛天神の境内に社祠ができたので何の神かと尋れば貧乏神の社だという。この宮に詣でて貧乏を免れようと願うならば、その霊験があるというのだ。この起立を尋れば、同じ小石川に住む旗本が代々貧乏だったので家内を思う事も叶わなかった。よって、明暮ともに難儀していたという。
そこで、この人はある年の暮れに貧乏神の絵を描いて、これに神酒や洗米など供えて「我らは数年貧窮に喘いでいます。思いが叶わぬことは是非も無いですが、いつも貧しければ他に愁いもありません。ひとえに尊神が守護されており、数代我らを守り給う御神であるならば、何卒一社を建立して尊神を崇敬なすべき間、少しばかり貧窮を免れて福分に移り替われる様、どうかお守りください」と祈願を捧げた。
そして、小さな祠を屋敷内に立てて朝夕祈っていると、御利益なのか少しばかりの幸を得ることができたので、心が安らいだ時に牛天神の別当にこの事を語り、境内の隅に祠を移したいと相談してみたところ、別当も面白がって許諾したので、今は天神の境内に移されたのだという。これによって貧しい身の上の者は この社を詣でて祈るようになったのだ。云々。
『兎園小説(窮鬼)』
文政4年(1821年)の夏頃、江戸番町の禄高の某武家の用人が主命を受けて下総の知行所に向かい、江戸から草加の宿の辺りで1人の法師と出会った。
その法師は40歳あまりに見え、顔色は青黒く、眼は堀の深い俗にいう鉄壺眼で、顔の形は鋭く尖って細面であり、古ぼけた溝鼠染の衣・白菅の笠・頭陀袋を身に着けていた。用人は法師と並んで歩くうちに、煙草の火を借りる仲になって、次第に言葉を交わすようになった。
用人が「貴方はどこからどこへ行くのですか?」と問うと、法師は「私は番町の某邸から越谷に行くところだ」と答えた。これを聞いた用人は訝しく思って「私はその某邸の用心です。私が見たことの無い人が屋敷に居るわけがありません。出家に似つかわしくない虚事をいわれるのですね」と言って嘲笑った。
すると、法師も嘲笑って「どうして貴方を騙す必要があるのか、単に貴方が私を見知らぬだけだろう。そもそも私は世にいう貧乏神である。貴方は昔のことは知らないだろうが、私は3代前の主人の頃から屋敷に居り、その頃から某邸には病人は常に絶えることはない。先代の両主も短命であった。ただ、これだけではなく、万事に幸が無くて常に貧窮しており、禄はあっても無いようなものである。それでも家が滅びないのは先祖の遺徳によるところである。この某邸では、このようなことがあっただろう…」などと、用人も知らない事を見ていたかのように語るので、用人は驚くばかりで返す言葉が無かった。
そこで窮鬼(貧乏神)は唖然とする用人を見て「恐れることはない。某邸は今の代で貧窮極まったので私が居る必要も無くなった。そこで私は他所へ移ろうと思う。よって、今から某邸の主には幸いなことが起き始め、代々重ねた借財なども返すことができるだろう。これを疑うことは無いように」と言った。
これに用人は落ち着きを取り戻して「では、貴方はどこに行かれるのか?」と問うと、窮鬼(貧乏神)は「私が向かう所は、そんなに遠くではない。貴方の主の近隣にある某屋敷に移るのだ。その移転までに少しばかりの暇ができたので、越谷に渡って知り合いを訪ねようと出向いたのだ。翌日には先の屋敷に越すつもりである。これから その屋敷は万事に幸が無くなり、遂に貧窮極まるだろう。そして貴方の主が今まで頭をもたげていたようになるのだ」と言い、これを他言しないようにと囁きつつ、越谷に着いた辺りで忽然と姿を消してしまった。
こうして用人は知行所に行って、村の役人と語らっていると、度々の借財によって無理だと思われていた用件も立ちどころに片付き、思ったよりも多くの借り入れをすることができたという。
この話は同年の6月下旬に蠣崎波響から聞いた話である。彼は用人と親しかったので、この話を用人から直接 聞いたという。この武家と用人の姓名も分かっている。しかし、奇談ということで世に憚って此処では明かさない。ただ、そんなに昔のことでは無いので、知っている人もいることだろう。
『太田神社由緒』
昔、小石川の三百坂に住んでいた貧しい旗本の夢枕に一人の老婆が立って「ワシはこの家に住み着いている貧乏神だが、居心地が良くて長らく世話になっている。そこで御礼をしたいのでワシの言うことを忘れずに行うように」と告げたので、旗本はお告げの通りに行った。すると、忽ち運が向いて旗本は裕福になった。
そのお告げとは「毎月の1日・15日・25日に赤飯と油揚げを供えてワシを祀れば福を授けよう」というものだった。これ以来、福の神になった貧乏神の話は江戸中に広まって、多くの人が参拝に訪れるようになったという。
スポンサーリンク
|
|