貧乏神 ― 貧乏をもたらす神 ―
貧乏神(びんぼうがみ)とは、貧乏をもたらす神のこと。
人や家に憑いてまわるといわれており、窮鬼と呼ばれることもある。
基本情報
概要
貧乏神とは特定の人や家に憑いて貧乏をもたらす神で、貧乏神に取り憑かれると金銭や食物に困るようになったり、常に家から病人が出たり、何をやっても幸福を得られなくなるといわれている。
貧乏神の姿については、顔色が悪く、痩せこけており、薄汚れた姿の見窄らしい老人で、手には渋団扇を持っているといわれることが多い。ただし、姿形については諸説あり、5寸(約15cm)ばかりの人形、見窄らしい格好をした壮年の法師、赤熊のような髪を生やした大童子、などといわれることもある。
貧乏神が取り憑く条件は定かではないが、好物の焼き味噌を作ると匂いに誘われて貧乏神が寄ってくるといわれている。また、怠け者や不自由に暮らす人間の様子を見るのが好きで、そういった人の家に入って押入れに住み着くという話もある。また、民間伝承でも貧乏神を引き寄せるという行為がいくつも伝えられている。また、貧乏神が嫌う物や行為も伝えられており、貧乏神を追い払うために敢えて嫌うことをする民間行事もある。
なお、貧乏神は中国由来の窮鬼と同一視されることもある。この窮鬼とは五帝の一人である顓頊の子で、生まれつき身体が弱く、いつもボロボロの衣服を着て、白粥ばかり食べていたため、窮子と呼ばれており、死後にいわゆる貧乏神として扱われるようになったので「送窮(送窮鬼)」という行事によって送り出したという。また、日本にも「貧乏神送り」と呼ばれる同様の行事があり、明治期まで大阪辺りで行われていたとされている。
貧乏神には「神として祀ることで福神に転じる」とする話もある。
『日本永代蔵』には「何をやっても貧しかった染物職人が敢えて嫌われ者の貧乏神を手厚く饗したところ、これに感銘を受けた貧乏神が商売に関する助言をした後に長者の家に移り住んだので、この職人は貧乏神の助言から着想を得て新しい染物を考案し、これによって財を為した」という説話が載っている。
『耳嚢』には「ある貧乏な旗本が、貧乏神を祀る社を建てて"貧窮を免れて福を授かれるように"と祈ったところ、僅かながらの幸を得られたので、その社を牛天神の境内に移すことになった」という奇談が載せられている。
また、東京都文京区にある牛天神北野神社の境内社である太田神社にも同様のいわれがあり、そこには「ある貧乏な旗本の夢に貧乏神と称する老婆が現れて"自分の言う通りにすれば福を授けよう"と言ったので、旗本がその通りにすると忽ち運が向いて裕福になった」という由緒が伝えられている。よって、当社では元々は貧乏神といわれる黒闇天女(弁財天の姉)を祀っていたが、先の逸話によって貧乏神を祓って福神を招き入れるという庶民の信仰が起こったという。ちなみに、この由緒にある貧乏神が教えた方法は「毎月の1日・15日・25日に赤飯と油揚げを供え、貧乏神を祀るならば福を授ける」といったものである。
この他にも長野県飯田市には貧乏神神社がある。当社は1998年に建立された比較的新しい神社であるが「自分自身の心に住み着く貧乏神を追い払う場所」と謳われており、神木を叩いたり蹴ったりしてストレスを解消することが御利益であるとしている。なお、当社の分社が東京都江東区や長野県茅野市などにある。
データ
| 種 別 | 神仏 |
|---|---|
| 資 料 | 『百物語評判』『耳嚢』『兎園小説』ほか |
| 年 代 | ~現代 |
| 備 考 | 窮鬼と呼ばれることもある |
・太田神社(東京都文京区春日1丁目5-2 牛天神北野神社内)
・貧乏神神社亀戸分社(東京都江東区亀戸6-31-1 サンストリート亀戸内)
・貧乏神神社(長野県飯田市大瀬木2728-1)
・貧乏神神社味噌蔵諏訪分社(長野県茅野市宮川4529 丸井伊藤商店内)
貧乏神に関する俗信
・焼き味噌(団扇で臭いを嗅ぐらしい)
・薄暗い場所(押入れ)
・汚い場所(貧乏神がいると腐った臭いがするとも)
・人が生活に困窮している有様(優雅な有様を嫌うとも)
・箸を揉む
・茶碗を叩く
・室内で体を揺する
・食事中に貧乏ゆすりをする
・夜中に口笛を吹く
・夜中に太鼓を叩く
・炉端を叩く
・炉の火をむやみに掘る
・部屋を汚くする
・身なりを汚くする
・部屋の空気を入れ替えない
・古い物を手入れもせずにずっと使う
・酢の物を食べる
・南天を植える
・握り飯に未醤の味噌を付けて食べる
・年末に大火を焚く
・生木を燃やして小豆を煮る
・貧乏神の嫌うことをする(引き寄せることの逆をする)
貧乏神に関する民間行事
大晦日の夜に囲炉裏で大火を焚くと貧乏神が熱がって逃げていき、代わりに小さい子供の姿をした福の神が現れるという。
吉川町では、1月7日に若木を山から取ってきて、14日にそれを燃やして小豆を煮るという行事があるという。これは「貧乏な爺が夜逃げした時に貧乏神が付いてきて『俺は生木を燃して小豆を煮るのが嫌いだ』と言ったので、翁が敢えて嫌う行為をすると、貧乏神は『俺の嫌いな事をするな』と言って銭を投げつけた」という故事から起こったとされる。
吉川町では、1月2日に水草と白膠木を山から取ってきて、15日にそれを燃やして粥を煮るともいわれる。これは「昔 貧乏な爺が生木を燃していると、天井にいた貧乏神が燻されたのに怒って『爺は何が嫌なのだ』と言ったので、翁は『俺は金に困っている』と答えると、貧乏神が千両箱を3つ投げつけた」という故事から起こったとされる。
大阪では明治10年(1877年)頃まで「貧乏神送り」という行事があったという。これは毎月の晦日に船場の商人の家で皿上にした焼き味噌を作り、それを番頭が持って家々を回って匂いを充満させ、頃合いを見計らって焼き味噌を2つに折る。こうすることで家から出てきた貧乏神が好物の焼き味噌に閉じ込められるので、番頭はその焼き味噌を川に流して貧乏神を追い払い、番頭自身も味噌の匂いをしっかり落として帰ったという。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
|
|
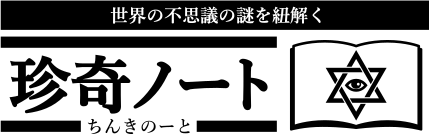

コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿