窮鬼 ― 貧乏神の起源とされる鬼 ―
窮鬼(きゅうき)とは、貧乏神あるいは生霊のこと。
一説に古代中国の帝王である顓頊の息子が、窮鬼の起源であるとされている。
基本情報
概要
窮鬼は、貧乏神あるいは生霊のことである。
一説に貧乏神の起源は、中国の民間伝承にある窮鬼であるといわれている。この窮鬼は、五帝の一人である顓頊(せんぎょく)の息子とされており、生まれつき体が弱くて背も低く、いつもボロボロの服を着て、白粥ばかり食べていたという。新しい服を与えても、着る前に破ったり、火で焼いて穴を作ってしまうので、周りの人々は「窮子」と呼んだという。
窮子は正月晦日に死んだので、宮中ではこの日を「窮子を送り出す日」と定めて葬り、これ以来 窮鬼と呼ばれて人々に恐れられる存在になったとされている。なお、唐代には窮鬼に由来する「送窮」あるいは「送窮鬼」と呼ばれる民間行事が起こったという。これは大晦日や正月晦日などに家内の貧乏神を送り出し、福禄の神を迎えて一年の幸福と安寧を祈る行事であり、日本にも「貧乏神送り」という似たような行事が存在する。
また、江戸時代の奇談集『兎園小説』には「窮鬼」という題目で、貧乏神の説話が載せられている。
生霊とされる所以は、平安時代の辞書である『和名類聚抄』に「窮鬼は『遊仙窟』で伊岐須太萬(イキスダマ)と注釈される」と説明されているからだと思われる。なお、窮鬼と書いてイキスダマと読まれることもある。
データ
| 種 別 | 妖怪、鬼 |
|---|---|
| 資 料 | 『和名類聚抄』ほか |
| 年 代 | 上古~現代 |
| 備 考 | 貧乏神・生霊と同一視される |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
|
|
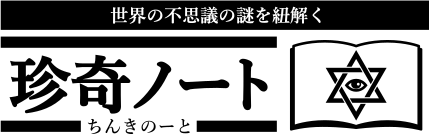

コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿