ウェンディゴ ― 北米先住民に伝わる飢餓の怪物 ―

ウェンディゴとは、北米の先住民の神話に登場する伝説上の怪物のこと。
飢餓の象徴のような怪物であり、人間を捕食する存在として語られている。
基本情報
概要
ウェンディゴは、北米の先住民であるアルゴンキン語族の伝承に登場する伝説上の怪物である。極寒の森林地帯に棲み、人間を捕食する存在として語られる一方で、人に取り憑き、その精神や肉体を蝕んでウェンディゴへと変貌させる悪霊的な側面も持つとされる。
名称については、ウィンディゴ、ウィチコ、ワインディゴなど、地域や言語によって複数の呼び名が存在する。いずれもアルゴンキン語族の文化圏に由来する呼称であり、共通して人を喰らう怪物、あるいは人を破滅へ導く存在を指す言葉として用いられている。
外見については伝承によって差があるが、痩せ細った人型の姿で、灰色がかった皮膚、落ちくぼんだ眼、唇のない大きな口と鋭い歯を持つ存在として描写されることが多い。背丈も人間ほどの大きさとして語られる場合から、森の木々よりも高い巨体として描かれる場合まで幅がある。
アルゴンキン語族の伝承において、ウェンディゴは単なる人喰いの怪物ではない。極限の飢餓状態に追い込まれ、共食いという重大な禁忌を犯した人間が変貌した姿、あるいはそのような人間に悪霊が取り憑いた結果として生まれる存在とされている。そのため、ウェンディゴは人間を捕食するだけでなく、人に憑依し、新たなウェンディゴを生み出すとも語られてきた。
物語の舞台となる地域は、カナダからアメリカ北部にかけての寒冷な森林地帯である。アルゴンキン語族の人々は、この怪物の伝承を通して、飢餓の恐怖、利己心、そして共同体の掟を破ることへの戒めを語り継いできたとされている。
現代では、本来の伝承から離れて単純にモンスターとして扱われることも多く、映画やアニメ、ゲームなどの作品に登場する存在としても広く知られるようになっている。
ウェンディゴ症候群
ウェンディゴ症候群とは、北米のアルゴンキン語族の文化圏で語られてきた伝承や信仰と深く結びついた精神状態の呼び名である。極寒や深刻な食糧不足といった極限状況の中で、「自分は人肉を食べたくなっている」「このままではウェンディゴになってしまう」といった強い恐怖や思い込みにとらわれる状態を指す。
19世紀から20世紀初頭にかけて、カナダやアメリカ北部では、この状態に陥ったとされる人物の記録が残されている。人肉を食べたいという衝動を訴えたり、自分が危険な存在になることを恐れて、隔離や処罰を求めた例もあったと伝えられている。こうした行動は、飢餓や孤立、共食いを最大の禁忌とする文化的価値観が重なった結果と考えられている。
現在では、ウェンディゴ症候群は医学的な病名としては認められていないものの、報告されている症状の多くは、統合失調症や重度のうつ状態、精神病性障害、極限ストレスによる精神錯乱などと共通点があるとされている。そのため、特定の精神疾患が、その土地の信仰や伝承によって「ウェンディゴ」という形で理解された例とみなされることが多い。
データ
| 種 別 | 伝説の生物 |
|---|---|
| 資 料 | アルゴンキン語族の神話 |
| 年 代 | 古代 |
| 備 考 | 映画の影響で角が描かれることがある |
アルゴンキン語族に伝わるウェンディゴ神話
嵐はあまりにも長く続き、人々はこのままでは餓死してしまうのではないかと恐れていた。
やがて風と吹雪が弱まり、ただの記憶のようになった頃、勇敢な戦士である父親は外へ出る決意をした。次の嵐はすでに地平線の彼方に見えていたが、食料を見つけられなければ家族は確実に飢え死にしてしまう。
彼はナイフと槍を手放さず、獣がよく通る道を進んだ。新しく積もった雪の上に、動物の足跡やわずかな動きでもないかと目を凝らしながらである。
森は氷と雪に覆われ、不気味なほど静まり返っていた。理性ある生き物は皆、巣穴の奥深くで眠っているようだった。それでも戦士は狩りを続けた。家族がどれほど追い詰められているかを、彼はよく知っていたからだ。
風がそっと吹く音以外、何も聞こえない静寂の中で、彼は奇妙な「シューッ」という音を耳にした。それはどこからともなく、同時にあらゆる方向から聞こえてくるようだった。
戦士は立ち止まり、心臓が激しく脈打つのを感じた。そのとき、目の前の道に血にまみれた足跡が現れた。
彼はナイフを強く握りしめた。どこかで、ウェンディゴが彼を見ているのだ。
ウェンディゴについては、幼い頃に父から教えられていた。木のように背の高い巨大な姿、唇のない口、ぎざぎざの歯。吐息は不気味なシューッという音を立て、足跡は血に染まっている。そして、その縄張りに足を踏み入れた人間――男も女も子どもも――すべてを喰らう存在だ。
だが、それでも運が良い方だった。時にウェンディゴは人間に取り憑くことがあり、その場合、取り憑かれた者は自らがウェンディゴとなり、かつて愛した人々を狩り、その肉を貪ることになるのだから。
戦士は悟っていた。ウェンディゴに勝つチャンスは一度きりだ。
それを逃せば死ぬ。あるいは――それ以上に恐ろしい運命が待っている。
彼は血の足跡からゆっくりと後ずさりし、あの不気味な音に耳を澄ませた。どちらの方向が強いのか。槍を片手に、ナイフをもう一方の手に握ったその瞬間、左手の雪山が爆ぜるように崩れ、木ほどもある巨体の怪物が飛び出してきた。
戦士は横に飛び、雪の中を転がった。衣服は雪に覆われ、迫り来る嵐の薄暗い夕暮れの中で、彼の姿は見えにくくなった。ウェンディゴは巨大な体を旋回させ、戦士は槍を投げつけた。槍は胸に突き刺さったが、怪物はまるで玩具のようにそれを振り払った。
戦士は小さな木の陰に身をかがめ、引き裂かれた雪の上を探し回る怪物の様子を窺った。
――あと一度だけ、チャンスがあるかもしれない。
ウェンディゴは彼の隠れ場所の上に立ち、鋭い目で木越しに彼の輪郭を捉えた。長い腕を伸ばし、身を屈めたその瞬間、戦士は怪物に抱きつくように飛び出し、ナイフを底知れぬ黒い眼に突き立てた。
ウェンディゴは激痛に吠え、刃は脳へと深く食い込んだ。怪物は彼を振り払おうとしたが、戦士は必死にしがみつき、何度も何度も眼と頭部を刺し続けた。
やがてウェンディゴは大量の血を流しながら倒れ、その巨体は危うく戦士を押し潰しかけた。戦士は何とか体を引き抜き、怪物を見つめた。その白い体は雪景色に溶け込み、血が眼や耳、頭皮から流れていなければ見分けがつかなかっただろう。
すると怪物の輪郭が霧のようにぼやけ、やがて消え去った。そこには、倒れた場所を示す血溜まりだけが残されていた。
恐怖と疲労で震えながら、戦士は家路についた。飢えで衰弱していたが、嵐は間もなく明けると分かっていた。ここで倒れれば命はない。
森の端まで来たとき、彼は一匹の赤狐と向かい合った。年老いて太った狐で、口元には白い毛が混じっていた。まるでウェンディゴを倒した褒美として差し出されたかのように、狐はじっと立っていた。
戦士は感謝の祈りを捧げ、その狐を仕留め、飢えた家族のもとへ持ち帰った。その肉は何日も家族を支え、最後の嵐が過ぎ去るまで命をつないだ。そして戦士は、再び安全に狩りへ出られるようになったのだった。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
|
|
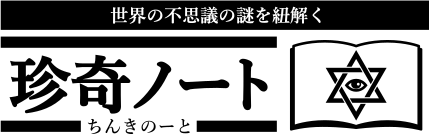
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿